

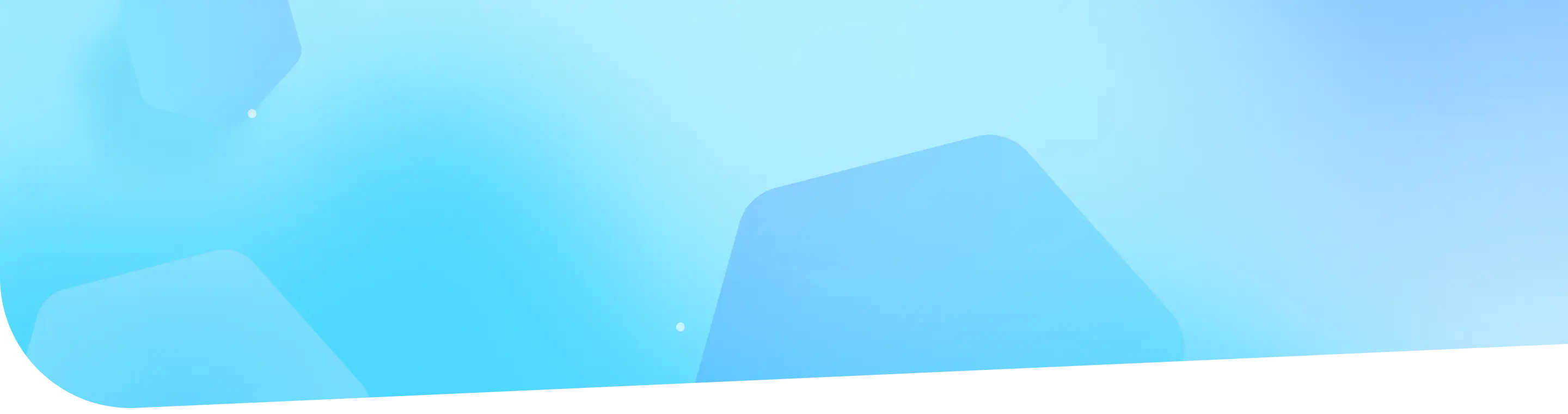
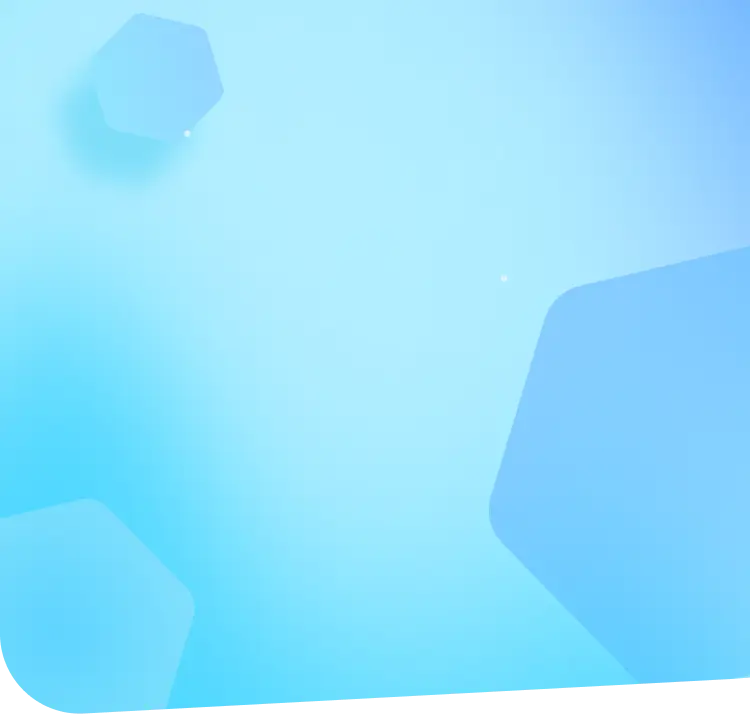
クレデンシャルは、ユーザーやシステムが「誰(何)であるか」を証明し、アクセスを許可するために使われる認証情報の総称です。漏えいすると攻撃者が正規ユーザーになりすまして侵入できるため、仕組みの理解と管理の精度がそのまま被害規模に直結します。この記事では、クレデンシャルの定義・種類・代表的な攻撃手法・管理の要点を、実務で判断できる粒度で整理します。
クレデンシャル(credential)は、認証(authentication)に用いられる情報・手段の総称です。認証とは、システムやサービスが「アクセスしてきた相手が、主張している本人(または正当なシステム)か」を確認する行為を指します。代表例は、パスワード、暗証番号(PIN)、ワンタイムパスワード(OTP)、証明書、秘密鍵、生体情報、認証トークンなどです。
クレデンシャルは「何を証明したいか」「どの程度のリスクを許容できるか」によって形が変わります。たとえばWebサービスのログインではIDとパスワードが一般的ですが、高い保証が求められる環境では、証明書や公開鍵暗号の鍵(秘密鍵)による認証、あるいはFIDO2/WebAuthnのようなフィッシング耐性のある方式が採用されます。
また、クレデンシャルは「情報そのもの」だけでなく、認証を成立させるための要素(ファクター)の文脈でも語られます。端末そのものはクレデンシャルというより所持要素ですが、端末内に格納された秘密鍵やトークンがクレデンシャルとして機能します。扱いを誤ると不正利用の起点になり得るため、クレデンシャルは“資産”として管理する必要があります。
実務では、クレデンシャルが「認証(本人確認)」だけでなく「認可(権限付与)」にも関わる点を整理しておくと誤解が減ります。認証に成功した後、システムはセッションIDやアクセストークンなどを発行し、その後のアクセスを継続的に許可します。つまり、ログイン後に発行されるトークン類も、奪われれば乗っ取りに直結する重要なクレデンシャルです。
例として、Webアプリでは次のような経路でクレデンシャルが扱われます。
「どこに」「どの形式で」存在するかを把握しないと、保護設計も監査も成立しません。特にクラウド利用やCI/CDの普及により、APIキーやサービスアカウント鍵がコード・設定・環境変数に散在しやすく、棚卸しと統制が重要になります。
クレデンシャルは「正当なユーザーだけがアクセスできる状態」を実現する中核です。奪われると攻撃者は“正規の手続き”でログインできてしまい、ネットワーク境界やマルウェア対策をすり抜けることがあります。さらに、権限の強いアカウントや、横展開に使える認証情報(管理者資格情報、サービスアカウント、Kerberosチケットなど)が狙われると、侵害は短時間で拡大します。
そのため対策は、次の3方向を同時に設計するのが現実的です。
なお「パスワードは定期的に変更すべき」という一般論は、運用負荷や形骸化(使い回し・単純化)を招くことがあります。近年は、漏えい・侵害が疑われる場合の変更を重視し、根拠なく周期変更を強制しない考え方も示されています。
クレデンシャルは「知識」「所持」「生体」という認証要素(ファクター)で整理すると理解しやすくなります。ただし実務では、ログイン後に発行されるトークンや、システム間連携で使う鍵・証明書も同等に重要です。ここでは現場で遭遇しやすい代表例を整理します。
ユーザー名やメールアドレスは、厳密には「識別子(identifier)」であり単独では本人確認になりません。ただし攻撃者にとっては狙うべきアカウントを特定する手がかりになります。ログインやパスワード再設定の画面で「そのユーザーは存在しません」と明示すると、ユーザー列挙(有効アカウントの特定)に悪用されやすいため、エラーメッセージの統一などが有効です。
パスワードは最も普及したクレデンシャルですが、使い回し・漏えい・推測攻撃の影響が大きいのが弱点です。複数単語で構成するパスフレーズは、長さを確保しつつ覚えやすい形で強度を上げられます。実務では「長さ優先」「サービスごとにユニーク」「既知漏えいパスワードの拒否」「パスワードマネージャの活用」を組み合わせるのが現実的です。
PINは短く入力しやすい一方、総当たりやのぞき見に弱くなりやすいため、試行回数制限や端末側の安全領域と組み合わせて成立させるのが基本です。オンラインで送る“短いパスワード”として使うより、端末内の鍵を解錠する用途(ローカル)で使う方が安全性を確保しやすい傾向があります。
OTPは短時間で失効するコードで、MFAの追加要素として広く使われます。ただしOTPにも限界があり、SMS OTPはSIMスワップや転送設定悪用のリスクがあります。また、フィッシングでリアルタイムに入力させる手口(中間者型)ではOTPが奪われることがあります。重要システムでは、プッシュ承認の番号一致や、フィッシング耐性のある方式(WebAuthn等)の検討が有効です。
秘密鍵は、クライアント証明書認証、SSH、コード署名、デバイス認証などで使われます。秘密鍵が漏えいすると「本人になりすまして署名できる」状態になるため、影響が大きくなりがちです。実務では、秘密鍵を端末の保護領域(TPM等)に保管し、エクスポートを制限する、証明書に失効(失効リスト・OCSP)と有効期限の運用を組み込む、といった設計が重要です。
ログイン後に発行されるトークンは、利用者から見ると“ログイン済み状態”を維持するための鍵です。奪われればパスワードを知らなくても乗っ取りが成立するため、クレデンシャルとして扱う必要があります。対策として、短命トークン、リフレッシュトークンの厳格管理、Cookie属性(Secure/HttpOnly/SameSite等)の適切化、重要操作時の再認証、端末準拠やIP変化時の追加検証などを組み合わせます。
システム間連携で使われるAPIキーやサービスアカウント鍵は、漏えい時に“無人で不正アクセスが継続する”リスクがあります。コードやリポジトリ、CI/CDの設定、環境変数、ログ出力に混入しやすい点が実務上の落とし穴です。秘密情報管理(シークレットマネージャ)、最小権限、定期ローテーション、シークレットスキャン、監査ログの整備が重要になります。
生体認証は、指紋、顔、虹彩、声紋などの身体的特徴や、キーストローク・操作パターンなどの行動特徴を用いて本人確認を行う技術です。利便性が高く、端末ロック解除や業務システムの認証で広く使われています。
ただし、生体情報をサーバー側に集約して照合する設計は、漏えい時の影響が大きくなります。実務では、端末内の安全領域で照合し、外部には結果(鍵の解錠や署名)だけを渡す設計が望まれます。
導入時は、誤検知・誤拒否、環境依存(手袋・マスク等)、なりすまし耐性(ライブネス)といった運用上の条件を評価する必要があります。
現場では、生体認証を単独で完結させるよりも、端末内の鍵管理やMFAの一部として組み込み、「漏えいしにくい」「漏えいしても被害を拡大しにくい」形に落とし込むことが重要です。
攻撃者は、脆弱性を突く前に「ログインできる状態」を作ろうとします。ここでは代表的な手口と、現場で効く対策の方向性を整理します。
漏えいしたID/パスワードの組み合わせを別サービスで試す攻撃です。被害はユーザーの使い回しに強く依存します。主な対策は、MFA、異常ログイン検知、レート制限・ボット対策、既知漏えいパスワードの拒否、パスワードのユニーク化(マネージャ推奨)です。
総当たりは1アカウントに対して多数の候補を試します。パスワードスプレーは、少数のよくあるパスワードを多数アカウントに対して試す手口で、ロックアウト回避を狙います。対策は、レート制限、段階的な追加検証(CAPTCHA等)、異常試行の検知、漏えいパスワード拒否、MFAの導入です。
偽のログインページに誘導して入力させる手口です。近年はMFAコードまでリアルタイムに詐取する中間者型もあります。対策として、フィッシング耐性のある認証(WebAuthn等)、重要操作時の追加認証、セッションのリスク評価(端末準拠・位置・異常行動)に加え、メール側の対策(なりすまし対策の整備)と利用者教育を組み合わせます。
フィッシングに限らず、マルウェア、ログの誤出力、ソースコードへの埋め込み、設定ファイル流出など、さまざまな経路でクレデンシャルが収集されます。実務上は「どこに、どの形式の秘密情報が存在し得るか」を棚卸しし、秘密情報のハードコード禁止、シークレットマネージャ導入、ログのマスキング、リポジトリのシークレットスキャン、最小権限を徹底することが重要です。
パス・ザ・ハッシュは、認証情報(ハッシュ)を盗み、そのハッシュを用いて認証を突破する攻撃です。パス・ザ・チケットはKerberosのチケットを盗んで悪用する攻撃です。いずれもパスワードを知らなくても侵入できる点が特徴です。対策は、特権の最小化、資格情報保護機能の活用、横展開を想定した監視(不審な認証の相関分析)、重要サーバーへのアクセス経路分離(踏み台・特権アクセス管理)などを多層で設計します。
クレデンシャル管理の目的は「奪われないこと」だけではありません。万が一奪われても被害を最小化し、早期検知・復旧できる状態を作ることが実務のゴールです。
加えて、ログイン面の防御(レート制限、ボット対策、段階的ロック、追加検証の適用条件)を整備し、成功・失敗のログを監視できる状態にします。
MFAはパスワード漏えい時の防波堤になりますが、方式選定と運用設計が重要です。守りたい資産が重要なほど、フィッシング耐性(WebAuthn等)、プッシュ通知の誤承認対策(番号一致等)、端末準拠や位置情報を使った条件付きアクセスを検討します。
また、バックアップコードの保管、端末紛失時の復旧、ヘルプデスクでの本人確認、例外運用(MFA免除)の統制を曖昧にすると、攻撃者にとっての抜け道になります。
被害を拡大させやすいのは、管理者権限や広範囲にアクセスできるサービスアカウントです。一般ユーザーと同じ運用に載せるのではなく、次のように別扱いします。
「ログイン後に発行されるもの」もクレデンシャルである、という前提に立つと対策が具体化します。短命トークンの採用、リフレッシュトークンの厳格管理、Cookie属性の適切化、異常検知時のセッション失効、重要操作の再認証などにより、奪われても被害を局所化できます。
クレデンシャル管理は継続運用で効果が出ます。最低限、次を定期点検します。
侵害をゼロにできない前提で、検知・封じ込め・復旧の手順(インシデント対応)まで整備しておくと、被害拡大を防ぎやすくなります。
クレデンシャルは個人データや業務データへの入口です。入口が破られると、個人情報の漏えい・不正利用に直結します。そのため、クレデンシャル管理はセキュリティだけでなく、プライバシー保護の観点でも重要です。
データ保護の枠組みは、特定のパスワード要件を一律に定めるというより、リスクに応じた適切な技術的・組織的措置を求める考え方が基本です。実務では「なぜその認証方式・運用が適切と言えるか」を説明できるよう、リスク評価と統制の根拠(方針、運用手順、ログ、監査結果)を整備することが重要です。
クレデンシャルは認証の根幹であり、漏えいすると“正規ログイン”として侵害が進むため、技術対策だけでなく運用設計まで含めた管理が欠かせません。種類(パスワード、OTP、鍵・証明書、トークン、APIキー等)と、攻撃手法(スタッフィング、スプレー、フィッシング、パス・ザ・ハッシュ等)を押さえた上で、MFA・最小権限・シークレット管理・ログ監査・セッション制御を組み合わせることが、実務で効く基本戦略です。
ユーザーやシステムが正当であることを証明するために使う認証情報の総称です。
含めて扱われることが多いですが、IDは識別子であり、単独では本人確認になりません。
守るべきです。奪われるとパスワードを知らなくてもログイン済み状態を乗っ取られる可能性があります。
侵害兆候がある場合の変更は重要ですが、根拠なく周期変更を強制すると形骸化することがあるため運用設計が必要です。
漏えいしたIDとパスワードの組み合わせを別サービスで試して不正ログインする攻撃です。
完全には防げません。リアルタイムに入力させる手口では奪われることがあるため、方式選定と追加対策が重要です。
あります。WebAuthn/FIDO2などのフィッシング耐性のある方式は、偽サイトでの認証情報詐取に強い設計です。
システム間連携が不正に実行され、データ参照や操作が継続的に行われる可能性があります。
重要システムへのMFA適用、特権アカウントの最小化、シークレット管理、認証ログ監視を優先するのが現実的です。
関係があります。入口が破られると個人データの不正閲覧や持ち出しに直結しやすいためです。








![【徹底解説】ガイドライン改定が変える! 自治体DXとセキュリティの未来[座談会]の画像](/media/QujiLanrdXYhfYYS10PniOHWKMGSJplx03pkFEiZ.png)
![【徹底解説】ガイドライン改定が変える! 自治体DXとセキュリティの未来[座談会]の画像](/media/QujiLanrdXYhfYYS10PniOHWKMGSJplx03pkFEiZ.png)

