

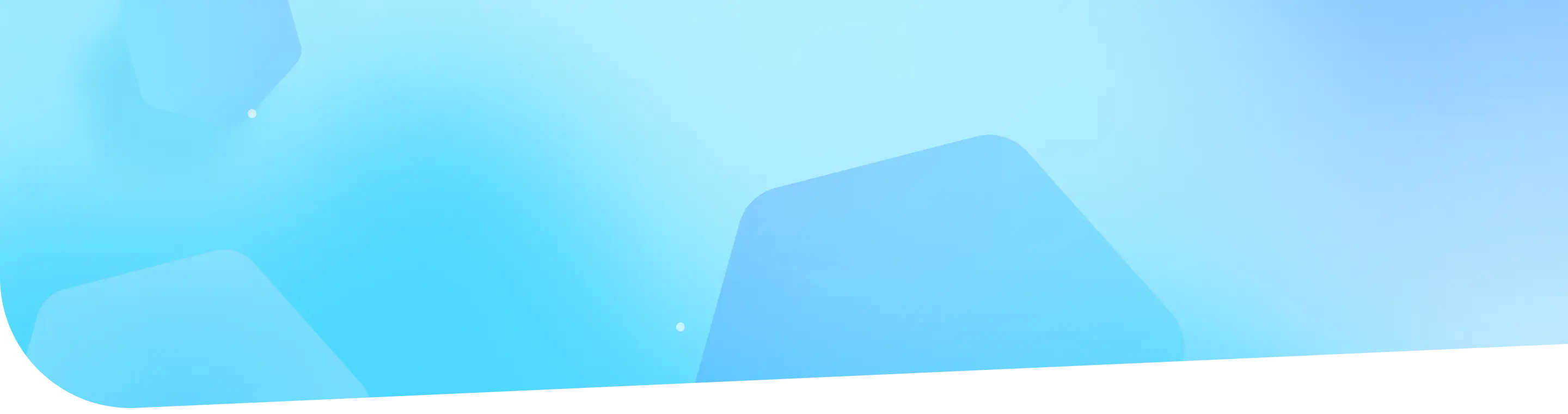
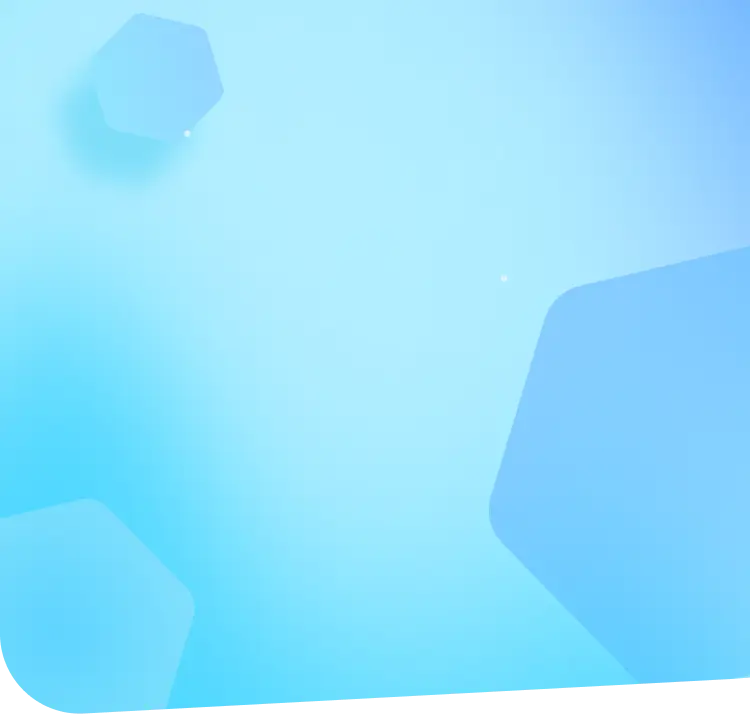
UnsplashのRodion Kutsaievが撮影した写真
スマートフォンやパソコンが普及し、行政手続きや買い物、学習、医療の予約までオンライン化が進む一方で、年齢・所得・地域・障害の有無などによって「使える人/使えない人」の差が生まれています。これがデジタルデバイドで、個人の不便さにとどまらず、企業の顧客接点や人材確保、地域の活力にも影響します。この記事では、デジタルデバイドの定義と要因、社会・企業への影響、解消に向けた取り組みを整理し、自分たちがどこから手を付けるべきか判断できる材料を提供します。
デジタルデバイドとは、情報通信技術(ICT)へのアクセスや利用における格差を指す概念です。この格差は、社会的・経済的な要因によって生じ、個人や企業、地域社会に大きな影響を与えます。デジタル化が急速に進む現代社会において、デジタルデバイドへの対策は重要な課題となっています。
デジタルデバイドは、ICTへのアクセスや利用機会の不平等を表す用語です。ここでいう「格差」は、単に端末の有無だけではありません。例えば、端末はあっても「設定が難しい」「入力が苦手」「サポートが受けられない」「安全に使える自信がない」といった理由で、サービスを十分に利用できない場合も含まれます。
デジタルデバイドが生じやすい代表的な要因は、次のように整理できます。
これらの要因が複合的に作用し、社会全体のデジタル化の進展を阻害する可能性があります。
デジタルデバイドが生じる要因は相互に関連し、単独ではなく「重なって」格差を深めることが多い点に注意が必要です。例えば、地方在住で回線が不安定なうえ、相談相手が少なく、結果として学習機会も得にくい、といった形で影響が連鎖します。
| 要因 | 説明 |
|---|---|
| 経済的要因 | 所得格差によるデバイスや通信環境へのアクセスの差(端末更新が難しい、通信費負担が重いなど) |
| 地理的要因 | 都市部と地方におけるICTインフラ整備状況の格差(回線品質、店舗・窓口の距離、支援拠点の有無など) |
| 年齢的要因 | 高齢者のICTリテラシーの低さと若年層とのギャップ(操作不安、詐欺への警戒、学習機会の不足など) |
| 教育的要因 | ICT教育の機会や質の不平等による知識・スキルの格差(学校・家庭環境、支援者の有無など) |
| 身体・認知的要因 | 視覚・聴覚・身体機能、認知特性などにより操作が難しくなる場合(アクセシビリティ不足が障壁になる) |
| 心理・文化的要因 | 失敗への不安、セキュリティ不安、周囲に聞けない雰囲気などが利用を抑制する |
これらの要因は相互に関連しており、複合的に作用することでデジタルデバイドを深刻化させます。
デジタルデバイドは、次のような影響をもたらします。ポイントは「オンライン化が進むほど、差が“見えにくく”なる」ことです。表面上は手続きが便利になっても、利用できない人は置き去りになりやすく、結果として不利益が固定化する恐れがあります。
これらの影響は、社会の公平性や持続可能性を脅かす要因となります。
デジタルデバイドは、企業活動にも大きな影響を与えます。特に「顧客」「人材」「業務運用」の3つの観点で影響が出やすく、放置するとコスト増や信用低下につながる可能性があります。
企業には、社会全体のデジタル化促進に貢献することが期待されています。デジタルデバイド解消に向けた取り組みは、社会的責任だけでなく、顧客基盤の拡大や業務品質の向上という実利にもつながります。
デジタルデバイドは世界的な課題として認識されています。先進国と途上国の間では、ICTインフラの整備状況や国民のICTリテラシーに差が見られます。この格差は、経済発展や社会的不平等に影響を及ぼし、国際的な課題となっています。
また、国単位の差だけでなく、同じ国内でも都市部と地方、所得層、教育機会の差によって格差が広がることがあります。つまり、デジタルデバイドは「国境問題」であると同時に「国内問題」でもあります。
日本国内でもデジタルデバイドは存在します。例えば、オンライン申請やキャッシュレス、学校・自治体のデジタル連絡などが広がるほど、「使えること」を前提にした場面が増えます。その結果、機器操作や設定が苦手な層、回線環境が整いにくい層、支援者が近くにいない層が不利になりやすい構造が生まれます。
また、経済的な理由から端末更新が難しい、通信費負担が重い、学習機会が得にくいといった状況も、利用格差を固定化させる要因になります。これらの格差は、情報アクセスの不平等を生み、社会参加の機会を制限する可能性があります。
デジタルデバイド解消は「回線を整備すれば終わり」ではありません。アクセス面(つながる)と利用面(使える)を分けて考えることが重要です。
これらの課題に対し、政府・自治体・企業・教育機関が連携し、包括的な取り組みを進めることが求められます。
デジタルデバイド解消は、次の点で重要な意義を持ちます。
デジタルデバイド解消は、単なる技術的な課題ではなく、社会全体の包括的発展に関わる重要なテーマです。企業においても、デジタルデバイド解消への取り組みは、社会的責任の観点だけでなく、顧客体験の向上や人材戦略の面からも重要となります。
政府・自治体は、デジタルデバイド解消に向けて重要な役割を担っています。ICTインフラの整備に加えて、住民向けのデジタル相談窓口、講習会、端末利用支援など、「使える状態」を作る施策が鍵になります。
また、行政サービスをオンライン化するほど、代替手段(対面・電話・郵送など)の設計や、わかりやすい案内の整備も重要になります。これらの取り組みは、地域間格差の是正や世代間のデジタルリテラシー向上に寄与することが期待されます。
企業や各種団体も、デジタルデバイド解消に向けた取り組みを進めています。例えば、低価格端末や料金プランの提供、地域での講習会支援、NPOとの連携などがあります。
企業側の実務では、次のような観点が取り組みの軸になります。
企業・団体の取り組みは、政府・自治体の施策を補完し、デジタルデバイド解消を加速させる役割を果たします。
教育機関は、将来のデジタル社会を担う人材を育てる中核です。操作方法だけでなく、情報の信頼性を見抜く力、個人情報の扱い、詐欺や偽情報への対処といった「安全に使う力」も含めて学ぶことが重要になります。
教育機関におけるデジタルリテラシー教育は、長期的なデジタルデバイド解消に寄与します。加えて、生涯学習の観点から、社会人向けのICT教育プログラムの提供も重要でしょう。
デジタルデバイド解消は、個人レベルの取り組みも重要です。例えば、家族や近隣の人が「一緒に設定する」「困ったときの相談先を作る」「詐欺対策の基本を共有する」だけでも、利用のハードルは下がります。
また、支援する側は「全部やってあげる」よりも、「本人が自分でできる状態」を作ることが大切です。よく使う手順をメモにする、同じ画面構成で説明する、失敗しても戻れる方法を教えるなど、小さな工夫が定着につながります。一人ひとりの意識と行動の積み重ねが、デジタルデバイドのない社会の実現につながるのです。
デジタルデバイド解消に向けては、政府・自治体、企業・団体、教育機関、そして個人が、それぞれの立場で役割を果たし、連携を深めることが重要です。多様な主体の協力により、効果的な取り組みが可能となるでしょう。
デジタルデバイドが縮小すると、より多くの人が教育、就労、行政サービス、医療、金融などの機会にアクセスできるようになります。ICTへのアクセスと利用機会が広がることで、多くの人々がデジタル技術の恩恵を享受できるようになります。結果として、業務の効率化や新たなサービスの活用が進み、生産性向上に寄与します。
利用可能な人が増えるほど、企業は新たな顧客層にサービスを届けられます。これまで「難しそう」「不安」と感じていた層が使えるようになれば、市場は広がります。企業は、多様な顧客のニーズに対応したサービスやプロダクトを開発することで、新たな市場を開拓できるでしょう。
また、デジタルデバイド解消を支援する製品・教育・サポートサービス自体も、社会課題解決型のビジネス領域として注目されます。
多様な人がデジタル参加できる環境は、アイデアの源泉を増やします。利用者が偏らなければ、サービス改善のフィードバックも偏りにくくなり、より多くの生活・業務実態に沿った改善が進みます。企業は、多様な人材の協働により、社会課題の解決につながる革新的なソリューションを生み出せるでしょう。
デジタルインクルージョンとは、誰もがデジタル社会に参加し、その恩恵を享受できる状態を指します。年齢、所得、居住地域などに関わらず、全ての人々にデジタル技術へのアクセスと利用機会が提供されることで、社会の発展が促進されます。
企業にとっても、利用のハードルを下げる設計は顧客体験の向上につながり、結果としてブランドの信頼性やレジリエンスを高める要素になります。
デジタルデバイドとは、ICTへのアクセスや利用における格差を指す概念であり、年齢・所得・地域・教育機会などの要因によって生じます。この格差は、社会的不平等や機会損失、企業の市場縮小やサポート負荷増大など、様々な影響をもたらします。解消に向けては、政府・自治体、企業・団体、教育機関、そして個人が連携し、インフラ整備だけでなく、学習機会の確保、支援体制の整備、サービス設計の改善を含む多角的な取り組みが重要です。デジタルデバイドの解消は、生産性向上や新たな市場の創出、イノベーション促進、そしてデジタルインクルージョンの実現につながります。
いいえ。端末や回線があっても、操作不安や支援不足などで利用できない状態も含みます。
デジタルデバイドは格差の状態を指し、デジタルインクルージョンは誰もが参加できる状態を目指す考え方です。
十分ではありません。学習機会、相談先、わかりやすいサービス設計など「使える状態」を作る施策が必要です。
潜在顧客の取りこぼしやサポート負荷増大が起きやすく、信頼低下につながる可能性があります。
本人が自分でできる状態を作ることです。手順を固定し、失敗しても戻れる方法を教えると定着しやすくなります。
関係があります。不安が強いほど利用が進まないため、詐欺対策や安全な使い方の教育が重要です。
代替手段や相談窓口を整え、利用できない人が取り残されない導線を用意することが重要です。
操作だけではありません。情報の真偽判断や個人情報の扱い、詐欺対策など安全に使う力も含まれます。
利用率、手続き完了率、問い合わせ件数、講習参加者の継続利用などの指標で改善前後を比較します。
あります。身近な人の設定支援や相談先の共有、詐欺対策の基本を伝えるだけでも利用の壁を下げられます。











