

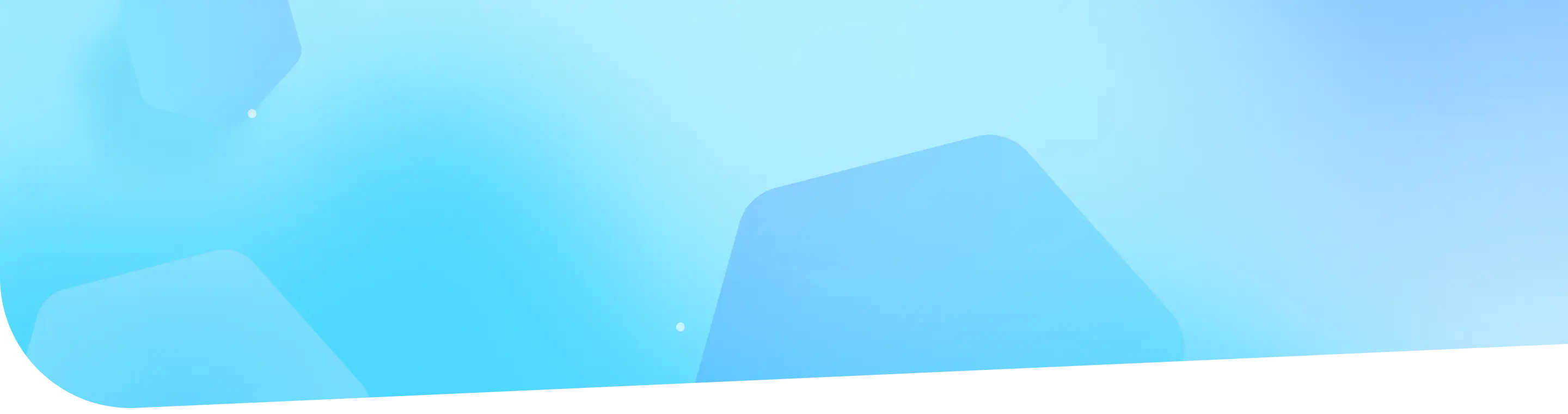
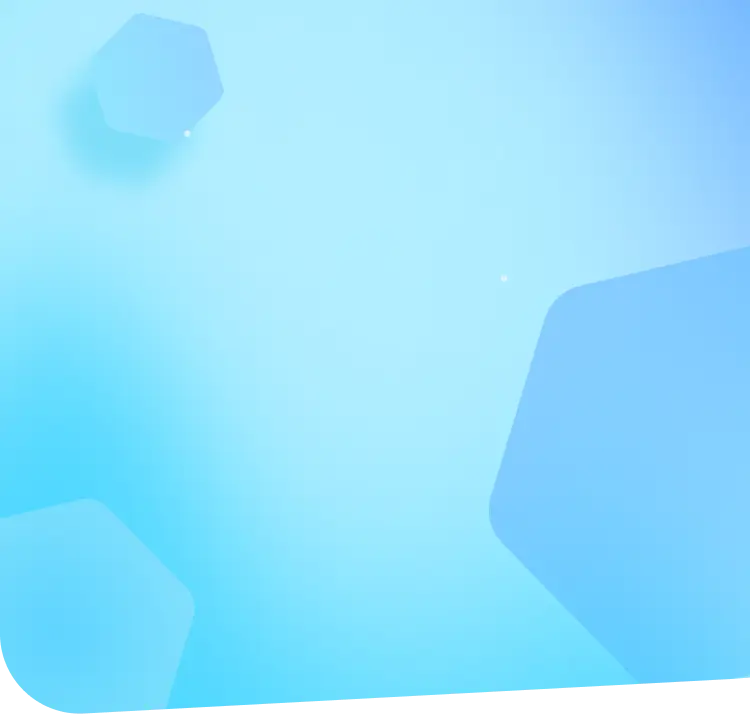
UnsplashのKelly Sikkemaが撮影した写真
近年、自然災害が頻発する中、あなたの会社の災害対策は万全でしょうか。災害時の情報収集や伝達の遅れは、事業継続や従業員の安全確保に大きな影響を及ぼします。この記事では、「災害情報のデジタル化」に焦点を当て、その必要性やメリット、具体的な進め方、そして企業にとっての意義をわかりやすく解説します。読み進めることで、災害に強い企業づくりのヒントをつかんでいただけるはずです。
災害情報デジタル化とは、災害時における情報の収集・整理・伝達・共有といった一連のプロセスを、デジタル技術を活用して効率化・高度化する取り組みを指します。近年、自然災害が頻発する中で、「迅速かつ正確な情報伝達」をいかに実現するかが、企業・自治体の大きなテーマとなっています。
従来の災害情報の伝達では、電話連絡や紙ベースのマニュアル、テレビ・ラジオによる情報提供などが中心でした。その結果、次のような課題が生じがちです。
デジタル化によって、これらの問題を大幅に軽減し、より迅速かつ正確な情報提供を実現できるようになります。また、デジタルデータとして蓄積することで、平時の分析や事後検証にも活用できる点が大きな特徴です。
災害情報のデジタル化には、次のようなメリットがあります。
これらのメリットにより、災害時の混乱を最小限に抑え、被害の拡大を防ぐことが期待されます。単純な「紙の電子化」ではなく、「意思決定に役立つデータ基盤づくり」として捉えることがポイントです。
一方で、災害情報のデジタル化には、次のような課題も存在します。
| 課題 | 説明 |
|---|---|
| システムの開発・導入コスト | デジタル化のためのシステム開発や導入には、初期費用・運用費用の両面で一定のコストがかかります。 |
| データの標準化と互換性 | 異なるシステム・部署・自治体間でデータを円滑に連携するには、フォーマットの標準化やインターフェース設計が必要です。 |
| セキュリティとプライバシーの確保 | 災害情報には、従業員の安否や所在地などの個人情報を含むこともあるため、適切なセキュリティ対策とプライバシー保護が不可欠です。 |
| 人材の育成と運用体制の整備 | システムを「入れて終わり」にしないためには、運用ルールの策定や、担当者のトレーニングなど継続的な体制整備が求められます。 |
これらの課題を把握したうえで、段階的に導入・改善を進めることが、無理のないデジタル化推進につながります。
現在、国や自治体、民間企業などが連携しながら、災害情報のデジタル化に取り組んでいます。具体的には、次のような取り組みが進められています。
今後は、こうした取り組みをさらに加速させ、より高度かつ実践的な「災害情報デジタル基盤」を整備していくことが求められます。企業においても、自社システムを災害に強いものへアップグレードすることで、事業継続性を高めると同時に、社会的責任を果たすことができるでしょう。
災害情報のデジタル化を進めるには、「情報収集」「情報管理」「情報発信」「双方向コミュニケーション」の各段階において、適切な施策を組み合わせることが重要です。ここでは、それぞれの段階で考えられる具体的な方法を整理します。
災害時の情報収集は、スピードと正確性が命です。デジタル技術を活用することで、次のような多角的な情報収集が可能になります。
これらの手段を組み合わせることで、現場の状況をリアルタイムかつ多面的に把握することが可能になります。
収集した情報を「点在させたまま」にしておくと、せっかくのデータを十分に活かせません。クラウドベースの情報管理システムを導入し、一元管理することで、次のようなメリットが得られます。
情報の一元管理により、関係者間で「同じ情報」を共有しながら意思決定できるようになり、現場の混乱を抑えることができます。
収集・整理した情報は、「必要な人に」「必要なタイミングで」「分かりやすく」届けてこそ意味があります。デジタル技術を活用した情報発信の主な手段は次の通りです。
| 方法 | 説明 |
|---|---|
| Webサイトでの情報公開 | 災害情報専用ページを用意し、避難情報・被害状況・復旧状況などを随時更新する。 |
| SNSを活用した情報拡散 | Twitter(X)やFacebookなどのSNSを活用し、速報性の高い情報を短いメッセージで素早く共有する。 |
| メールやSMSによる通知 | 従業員や登録ユーザーに対して、一斉配信で重要情報を確実に届ける。 |
| スマートフォンアプリの活用 | 専用アプリを通じてプッシュ通知を行い、重要なアラートを見落としにくくする。 |
複数のチャネルを組み合わせることで、情報を必要とする人に「届かない」「気づかれない」といったリスクを抑えられます。
災害時には「一方通行の情報提供」だけでなく、「現場からの情報」を受け取り、対応につなげることも重要です。双方向コミュニケーションを実現するための例として、次のような仕組みが挙げられます。
双方向のやり取りを仕組み化することで、現場のニーズを的確に把握し、きめ細かな支援や優先順位付けに役立てることができます。
以上のように、情報収集・一元管理・情報発信・双方向コミュニケーションの各段階でデジタル技術を活用することが、災害情報デジタル化の大きな柱となります。企業においても、自社の規模や業種に合わせて、できるところから段階的に導入を進めることが重要です。
災害情報のデジタル化を「形だけ」に終わらせず、実際に機能する仕組みにするためには、いくつか意識しておきたいポイントがあります。ここでは、平時からのシステム構築、関係機関との連携、利用者目線でのUI/UX設計、セキュリティ対策の4つの観点から解説します。
災害情報のデジタル化を効果的に機能させるためには、平時からシステムを構築し、運用体制を整えておくことが欠かせません。具体的には、次のような取り組みが推奨されます。
「災害が起きてから慌てて使い方を確認する」のではなく、平時から習熟しておくことで、実際の有事の際にシステムが真価を発揮します。
災害対応は、企業だけで完結するものではありません。自治体、防災関係機関、インフラ事業者、取引先企業などとの連携が不可欠です。連携を強化するためのポイントは次の通りです。
関係機関との連携が強化されるほど、災害対応のスピードと正確性は向上します。
災害時は、利用者にとって心理的な余裕が少ない状況です。そのため、住民・従業員・関係者など、利用者の視点に立ったUI/UX設計が重要になります。
| ポイント | 説明 |
|---|---|
| シンプルで直感的な操作性 | 複雑な操作や専門用語を避け、誰でも迷わず使える画面構成にする。 |
| わかりやすい情報の構造化 | 「今すぐ必要な情報」と「詳細な情報」を整理し、優先度の高い情報にすぐアクセスできるようにする。 |
| アクセシビリティの確保 | 高齢者や障がいのある方にも配慮した文字サイズ・色使い・音声読み上げ対応などを検討する。 |
| マルチデバイス対応 | PC、スマートフォン、タブレットなど、多様な端末から利用しやすいレスポンシブデザインを採用する。 |
利用者目線で設計されたシステムは、ストレスの少ない情報取得を実現し、誤操作や見落としのリスクを減らすことにもつながります。
災害情報には、従業員の安否情報や拠点の被害状況など、機微な情報が含まれることも多く、セキュリティ対策は極めて重要です。主な対策の例は次の通りです。
セキュリティ対策を徹底することで、情報漏洩や不正アクセスのリスクを最小限に抑えることができます。「安全な仕組みであること」そのものが、利用者の安心感にもつながります。
以上の4つのポイントを踏まえながら、災害情報デジタル化を進めることで、実際に役立つ仕組みへと育てていくことができます。
災害情報のデジタル化は、自治体や防災機関だけのテーマではなく、企業にとっても重要な経営課題の一つです。ここでは、事業継続計画(BCP)、従業員の安否確認、ステークホルダーへの情報提供、企業の社会的責任(CSR)の4つの観点から、その意義を整理します。
事業継続計画(BCP)は、災害やトラブル発生時に事業を継続・早期復旧するための計画です。災害情報のデジタル化は、BCPの実効性を高める重要な要素と言えます。
BCP策定の段階から「どのように災害情報を集め、どの基盤で共有・判断するのか」を設計に織り込むことで、紙のBCPに終わらない、実践的な体制につなげることができます。
災害発生時に、従業員の安全を確認することは企業の最優先事項です。デジタル技術を活用すれば、次のような方法で安否確認を効率的に行うことができます。
| 方法 | 説明 |
|---|---|
| 安否確認システムの導入 | 従業員がWebやアプリから安否・勤務地・自宅状況などを報告できる専用システムを用意する。 |
| メールやSMSによる一斉通知 | 登録された連絡先に対して一斉送信し、返信状況を一覧で把握する。 |
| 社内SNS・グループウェアの活用 | 部署やプロジェクト単位で情報共有し、未確認者のフォローにつなげる。 |
これらを組み合わせることで、従業員の安否をスピーディーかつ正確に把握し、必要な支援や指示を迅速に行うことができます。
災害発生時には、顧客・取引先・株主・地域社会など、さまざまなステークホルダーに対して適切な情報提供を行うことも重要です。デジタル技術を活用することで、次のような対応が可能になります。
ステークホルダーに適切な情報を提供することで、企業に対する信頼を維持・向上させ、風評被害や誤解の拡大を防ぐことができます。
災害情報のデジタル化は、企業の社会的責任(CSR)の観点からも重要な取り組みです。次のような点で意義があります。
CSRの一環として災害情報デジタル化に取り組むことで、社会的評価の向上とブランド価値の向上の両方を期待できます。
災害情報デジタル化とは、災害時の情報収集・管理・発信・共有を、デジタル技術で効率化・高度化する取り組みです。迅速かつ正確な情報伝達により、被害の拡大を防ぎ、事業継続や従業員の安全確保に大きく貢献します。
成功のポイントは、平時からのシステム構築と訓練、関係機関との連携、利用者目線のUI/UX設計、そして確かなセキュリティ対策にあります。企業にとっても、BCPの実効性向上、安否確認の効率化、ステークホルダー対応、CSRの実践という観点から、非常に重要なテーマです。
自社の状況に合わせて、できる部分から災害情報デジタル化を進めることで、災害に強い(disaster-proof)企業を目指していきましょう。
災害情報のデジタル化とは、災害時の情報収集・整理・伝達・共有などのプロセスを、デジタル技術を活用して効率化・高度化する取り組みを指します。紙や電話に頼るのではなく、システムやクラウド、アプリなどを使って、迅速かつ正確に情報を扱えるようにすることが目的です。
自然災害の頻発により、従業員の安全確保や事業継続への影響が大きくなっているためです。デジタル化することで、状況把握や安否確認、ステークホルダーへの情報提供を迅速に行え、被害の拡大防止と事業継続力の向上につながります。
まずは「どのような情報を、誰が、どのタイミングで必要としているか」を整理することが重要です。そのうえで、現状の連絡手段やシステムを棚卸しし、安否確認や情報共有など優先度の高い領域からデジタル化を進めていくとスムーズです。
安否確認システムを導入すると、従業員の状況を一括で把握でき、電話やメールの個別対応に比べて時間と手間を大幅に削減できます。また、誰が未回答か一目で分かるため、フォローすべき対象を明確にできる点もメリットです。
はい、有効です。シンプルな安否確認ツールやクラウドサービスを活用するだけでも、災害時の連絡ミスや情報の行き違いを減らせます。まずは規模に合った仕組みから導入し、必要に応じて段階的に拡張していくのがおすすめです。
従業員の安否や所在など機微な情報を扱うため、アクセス権限の管理、通信の暗号化、ログの取得・監査などが重要です。また、クラウドサービスを利用する場合は、提供事業者のセキュリティ方針や実績も確認しておくと安心です。
BCPでは、「状況を把握し、優先順位をつけ、対策を実行する」ことが求められます。災害情報のデジタル化は、その前提となる状況把握や情報共有を支える基盤であり、BCPの実効性を高める役割を担います。
SNSは速報性が高く有効な手段ですが、情報の正確性に注意が必要です。公式情報との突合せや、発信用アカウントのルール整備を行ったうえで活用することが重要です。また、社内向けと社外向けの使い分けも意識しましょう。
平時からシステムのテストや訓練を行い、操作に慣れておくことが大切です。また、連絡先リストや組織図の最新化、マニュアルの整備・更新、関係機関との連絡体制の確認なども、実際の災害時のスムーズな対応につながります。
いきなり完璧なシステムを目指すのではなく、「安否確認」「連絡手段の多重化」など、優先度の高いテーマから着手するのがおすすめです。そのうえで、自社の業務や地域のリスクに合わせて段階的に範囲を広げていくと、無理なく定着しやすくなります。











