

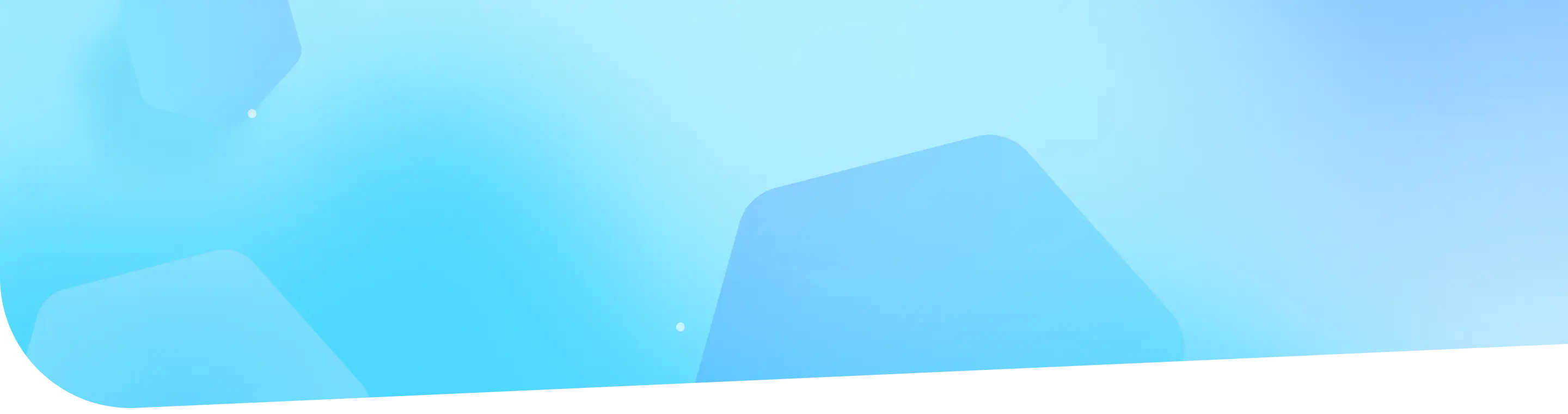
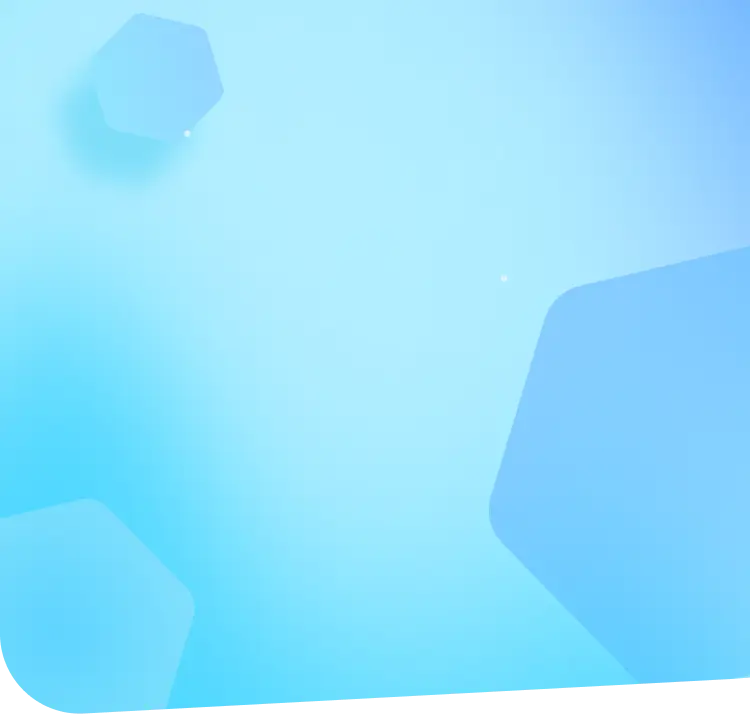
UnsplashのPhilippe Murray-Pietschが撮影した写真
昨今、インターネット上では「事実そのもの」だけでなく、事実の切り取り方や見せ方によって、受け手の判断が大きく揺さぶられる場面が増えています。この記事では、そうした有害な情報の一つであるマルインフォメーション(malinformation)について、概念・具体例・背景・対策までを整理します。読み終えたときに、SNSやニュースで見かける情報を「何が問題なのか」「どう確認し、どう対応するか」を自分で判断できる状態を目指します。
情報の問題というと「デマ(嘘)」を思い浮かべがちですが、実際には真実を材料にして人や組織を傷つけるケースもあります。それがマルインフォメーションです。嘘ではないため見抜きにくく、拡散した側も「事実を言っているだけ」と正当化しやすい点が厄介です。
3つの違いは、ざっくり言うと「情報が真実か」「発信者に害意があるか」です。
ポイントは、マルインフォメーションは「嘘ではない」ため、ファクトチェックで“完全否定”しづらいことです。議論の焦点は「真偽」だけでなく、「公開してよい情報か」「解釈や提示の仕方が妥当か」に移ります。
マルインフォメーションは、一般に真正な情報を用いて害を生む(cause harm)という枠組みで語られます。たとえば本物の文書・本物の写真・本物の発言でも、出し方次第で人を追い込み、組織を混乱させ、社会的対立を煽れます。
特徴としては、次の3点が典型です。
嘘ではなくても、害は現実に起きます。代表的には以下です。
拡散速度が速い環境では、後から丁寧に説明しても「最初に受けた印象」が残りやすく、訂正や補足が届きにくい点も課題です。
ここでは「真実を材料に害を作る」という観点で、ありがちな型を整理します(例は一般化しています)。
| 型 | 何が起きるか | 受け手が誤解しやすい点 |
|---|---|---|
| 切り取り(発言・動画) | 前後を省いて、発言の意図を逆転させる | 「本人が言っている=文脈も正しい」と思い込む |
| 本物の情報の晒し | 個人情報や内部資料を“正義”名目で拡散する | 公益と私刑の区別が曖昧になる |
| 統計の見せ方の誘導 | 分母や期間を変えて結論を印象操作する | 数字の見た目で納得してしまう |
| 事実の“並べ方” | 無関係な事実を並べて因果関係があるように見せる | 「偶然の相関」を「必然の原因」と誤認する |
対策は「嘘を見破る」だけでは足りません。文脈・目的・公開範囲・提示の仕方を合わせて評価する必要があります。
事実は反論されにくく、拡散時の心理的抵抗も小さいためです。「嘘じゃない」「引用しただけ」「みんな知るべきだ」という言い訳が成立しやすく、結果として“攻撃の材料”として使われます。
ニュースやSNSは速度が価値になりがちで、文脈確認(元資料の確認、全文確認、関係者の見解確認)に時間を割けない状況が生まれます。すると「断片」が流通し、断片をつないだストーリーが事実のように扱われやすくなります。
SNSは、強い感情を伴う投稿ほど反応を得やすい傾向があります。そのため、文脈を落としてでも“刺さる見せ方”が選ばれやすく、マルインフォメーションに向いた環境になりがちです。
マルインフォメーションは、完全否定が難しいため、訂正は「補足」や「背景説明」になりやすいです。しかし補足は拡散しにくく、誤解だけが残ることがあります。情報の受け手側にも、確認行動が求められます。
マルインフォメーションは「事実」を扱うため、単純な虚偽規制とは相性がよくありません。過度な規制は表現の自由や公益通報の価値を損ねる恐れがあり、線引きは慎重さが必要です。
個人ができる対策は、難しい技術ではなく確認の手順を持つことです。
誤解が広がっているときは、感情的に言い返すよりも、次のように最小限の要点で整えるほうが効きます。
「情報の正しさ」だけでなく、受け手が判断できる材料を揃えることが重要です。
企業側の基本は、平時から正しい一次情報にアクセスしやすい状態を作ることです。
マルインフォメーションは、社員個人の投稿が火種になることもあります。次の観点を押さえた教育・ガイドラインが現実的です。
「見つけてから考える」だと遅れます。最低限、次の型を決めておくと初動が安定します。
| フェーズ | やること | 判断の軸 |
|---|---|---|
| 検知 | 監視(社名・製品名・役員名)、通報窓口、関係部署共有 | 拡散規模/影響範囲/事実確認の難度 |
| 評価 | 「真偽」だけでなく文脈・晒し・権利侵害の有無を確認 | 訂正で済むか/法務対応か/沈静化優先か |
| 発信 | 一次情報を提示し、誤解ポイントを短く説明 | 過剰反応で増幅しないか |
| 追跡 | 追加説明、Q&A更新、社内外への説明の統一 | 同じ誤解が再燃していないか |
全てを社内で抱えるより、役割分担したほうが現実的です。
| 連携先 | 主な役割 |
|---|---|
| 法務・弁護士 | 権利侵害(名誉毀損、プライバシー等)の評価と手続き方針 |
| 広報/PR支援 | ステートメント設計、メディア対応、FAQ整備 |
| セキュリティ専門家 | 漏えい・侵害の可能性評価、技術的な再発防止 |
| ファクトチェック/検証協力 | 一次情報の整理、誤解ポイントの可視化 |
マルインフォメーションは、嘘ではなく事実を材料に害を生む点が特徴の情報です。そのため対策は「真偽判定」だけでは足りず、文脈・提示方法・公開範囲・受け手の確認行動まで含めて考える必要があります。個人は一次情報と文脈を確認する“型”を持ち、企業は平時から公式情報の置き場、教育、検知と初動のプレイブックを整えることが重要です。
事実(または真正情報)を材料に、文脈操作や晒しなどで人や組織に害を与える目的で使われる情報です。
ディスインフォメーションは意図的な虚偽(作り話や改ざん)ですが、マルインフォメーションは情報自体が本当でも害が生まれます。
ミスインフォメーションは誤情報を善意で広めてしまうケースで、マルインフォメーションは害意や攻撃性を伴う点が違います。
事実が含まれるため信憑性が高く見え、受け手が「嘘ではない」と判断して警戒心を下げやすいからです。
発言や動画の切り取り、統計の分母や期間のすり替え、無関係な事実の並置で因果関係を示唆する、個人情報の晒しなどがあります。
一次情報の確認、前後の文脈の補完、公開の妥当性の確認、結論より根拠(分母・定義・範囲)を見ることが有効です。
公式情報の集約(発表・FAQ・窓口)、更新履歴が分かる運用、SNS発信の権限と承認フローの整備が出発点です。
拡散規模と影響を評価し、真偽だけでなく文脈操作や権利侵害の有無を確認したうえで、一次情報と誤解点を短く示します。
事実が含まれるため単純な虚偽規制とは相性が悪く、表現の自由との調整も必要です。法務対応は他施策と併用します。
真偽が正しくても害が生まれるため、文脈・提示の仕方・公開範囲まで含めて評価し、補足説明や導線整備が必要になります。











