

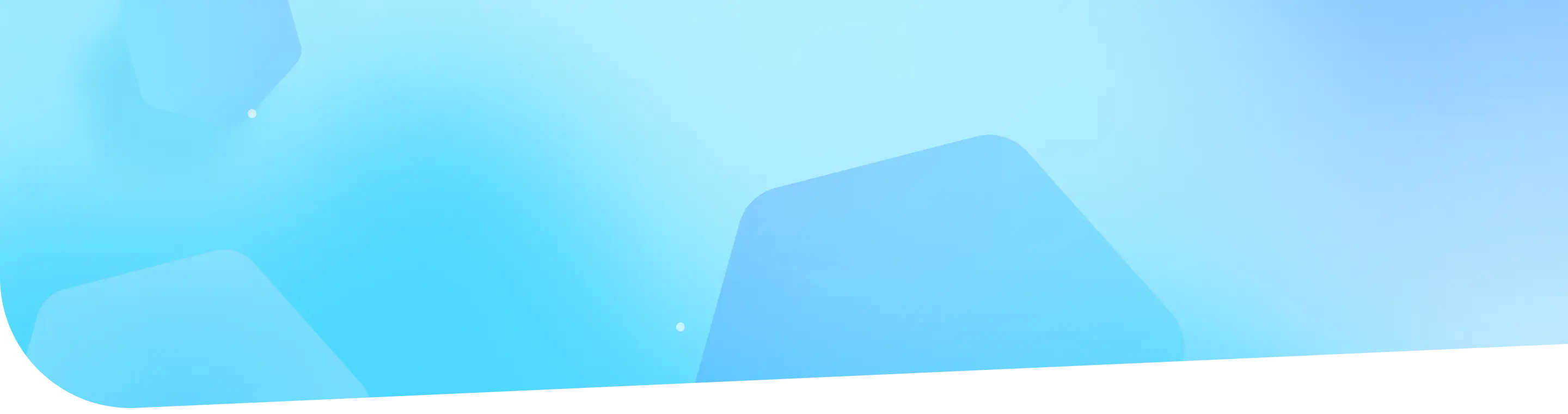
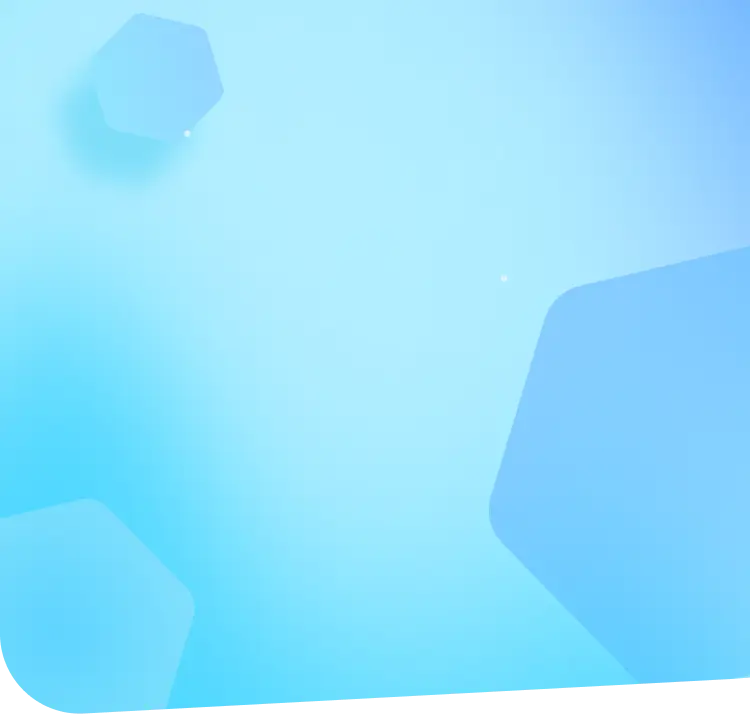
UnsplashのMārtiņš Zemlickisが撮影した写真
システムやサービスを導入した後、継続的に運用・維持していくために発生する費用を「ランニングコスト」と呼びます。このランニングコストが高くなると、事業の収益性が圧迫され、競争力の低下につながりかねません。この記事では、ランニングコストの基本的な概念から、その計算方法、削減のための具体的な方策、さらに経営戦略との関わりまでを、できるだけ具体的に解説します。
ランニングコストとは、システムやサービスを継続的に運用・維持するために必要となる費用のことを指します。これには、システムの保守管理費用、ソフトウェアライセンス料、ハードウェアの更新費用、電力料金、人件費などが含まれます。ランニングコストは、システムやサービスを導入した後に発生し続けるコストであり、導入から廃止までの長い期間を見据えて把握する必要があります。
イニシャルコストとは、システムやサービスを導入する際に初期段階で必要となる費用のことです。たとえば、ハードウェアの購入費用や導入作業の費用、初期設定の外注費用などが該当します。
一方、ランニングコストは、イニシャルコストとは異なり、システムやサービスを運用・維持するために継続的に発生する費用を指します。両者を合わせた総コスト(TCO:Total Cost of Ownership)で考えることで、導入候補ごとの「本当のコスト感」を比較しやすくなります。
ランニングコストが重要視される理由は、以下のような点に整理できます。
| 理由 | 説明 |
|---|---|
| 長期的なコスト削減 | ランニングコストを適切に管理することで、システムのライフサイクル全体でのコスト削減につながります。 |
| システムの安定運用 | 必要なランニングコストを確保することで、保守・監視・障害対応が滞らず、安定した運用が可能となります。 |
| ビジネスの継続性 | ランニングコストの水準を適切に保つことで、収益性を損なわずに長期的なビジネス継続を実現できます。 |
ランニングコストは、導入検討時にはイニシャルコストの陰に隠れがちな要素ですが、数年単位で見るとイニシャルコスト以上の差を生むことも多い、非常に重要な要素です。ランニングコストを適切に管理することで、システムやサービスのライフサイクル全体を通してコストパフォーマンスを最適化できます。
ランニングコストを算出する際には、以下のような考え方が一般的です。
ランニングコスト(年間) = 保守管理費用 + ソフトウェアライセンス料 + ハードウェア更新費用 + 電力料金 + 人件費 など
この式は、ランニングコストの主要な構成要素を一覧化したものです。実務では、ここにネットワーク回線費用やデータセンター利用料、監視サービス費用などが加わる場合もあります。実際のランニングコストは、システムやサービスの規模や複雑さ、運用形態(オンプレミスかクラウドか)、運用時間帯などによって大きく変動するため、この式はあくまでも整理の枠組みとして捉えることが重要です。
ランニングコストを現実的な水準で見積もるためには、以下のようなステップが有効です。
これらのステップを踏むことで、より精度の高いランニングコストの見積もりが可能となります。また、ランニングコストの見積もりは一度きりではなく、システムやサービスのライフサイクル全体を通して定期的に見直すことが重要です。技術の進歩やビジネス環境の変化に応じて、コスト構造が変わるためです。
ランニングコストを正確に算出するためには、以下のような情報が必要となります。
これらの情報を収集・分析することで、より精度の高いランニングコスト算出が可能になります。ただし、情報の収集には一定の時間と労力を要するため、導入検討の初期段階から計画的に着手することが重要です。また、収集した情報は定期的に更新し、常に最新の状態を維持する必要があります。
ここでは、ある企業のシステム運用におけるランニングコストの簡単な計算例を示します。
| 項目 | 年間コスト |
|---|---|
| 保守管理費用 | 500万円 |
| ソフトウェアライセンス料 | 200万円 |
| ハードウェア更新費用 | 100万円 |
| 電力料金 | 50万円 |
| 人件費 | 700万円 |
| 合計 | 1,550万円 |
この例では、年間のランニングコストは1,550万円となっています。ただし、これはあくまでも一例であり、実際のランニングコストは企業やシステムの特性、クラウド利用状況などによって大きく異なります。重要なのは、「自社の前提条件に合わせて何がどれくらいかかっているか」を可視化し、継続的に見直すことです。
ランニングコストを削減するためには、まずコストの発生源を明らかにし、「何にいくらかかっているのか」を把握することが出発点となります。以下のようなポイントに着目して見直しを進めると、具体的な検討がしやすくなります。
これらの見直しポイントを総合的に検討することで、ランニングコストの削減余地を発見しやすくなります。ただし、コスト削減だけを優先しすぎると、運用品質やセキュリティレベルの低下を招くおそれがあるため、「どこまでなら下げてもよいか」という基準を合わせて検討することが重要です。
ランニングコストを削減するための具体的な施策としては、次のようなものが考えられます。
これらの施策は単体でも効果がありますが、組み合わせて実施することで、より大きなコスト削減効果が期待できます。一方で、移行コストや変更によるリスクも発生するため、投資回収期間(何年でペイするか)を試算しながら優先順位をつけて進めることが大切です。
ランニングコストの削減を一時的なキャンペーンで終わらせず、継続的な取り組みとして根付かせるには、社内の体制づくりが欠かせません。たとえば、次のような取り組みが考えられます。
このような体制づくりにより、ランニングコスト削減への意識が組織全体に浸透し、施策の検討と実行を継続しやすくなります。ただし、組織変更や新たなルールづくりには一定の時間と調整が必要となるため、段階的に導入するのが現実的です。
ランニングコスト削減に成功した企業の事例を簡単に紹介します。
| 企業 | 施策 | 効果 |
|---|---|---|
| A社 | クラウドサービスへの移行 | ハードウェアコストを30%削減 |
| B社 | 運用の自動化 | 運用コストを40%削減 |
| C社 | 省電力機器の導入 | 電力料金を20%削減 |
これらの事例から、ランニングコスト削減には様々なアプローチがあり、自社の状況に合わせて適切な施策を選択・組み合わせることが重要であると分かります。ランニングコスト削減は一度の取り組みで完了するものではありませんが、小さな改善を積み重ねることで、数年後には大きな成果につながります。
ランニングコストの削減は企業にとって重要なテーマですが、同時にシステムやサービスの品質・安定性とのバランスも問われます。コスト削減と品質確保を両立するためには、現状の課題を正しく把握し、優先順位を明確にしたうえで、無理のない範囲から継続的に改善を進めていくことが求められます。
ランニングコストは、企業の競争力に大きな影響を与えます。ランニングコストを適切に管理することで、製品やサービスの価格競争力を高め、市場での優位性を確保しやすくなります。一方、ランニングコストが高止まりしていると、価格の引き下げ余地が小さくなり、競合他社との比較で不利になるリスクがあります。
また、ランニングコストの水準は企業の収益性にも直結します。ランニングコストを抑制できれば、その分だけ利益率が改善し、新たな投資や事業拡大に回せる資金が増えます。逆に、ランニングコストの増大が利益を圧迫している場合、成長投資に割ける余力が減り、中長期的な競争力低下につながるおそれがあります。
新たなシステムやサービスへの投資を検討する際には、イニシャルコストだけでなく、ランニングコストを含めた総コストで評価することが不可欠です。ランニングコストが想定以上に高くなると、投資の回収期間が長期化し、結果として企業の財務状況を圧迫する可能性があります。
そのため、投資判断の場面では、
といった観点を踏まえて検討することが重要です。また、ランニングコストを含めた投資対効果を継続的にモニタリングすることは、ITガバナンスの観点からも有効です。
ランニングコストは、ビジネスの持続可能性にも直接関わります。ランニングコストが高すぎる状態が続くと、売上が安定していても、利益が残らず事業の継続が難しくなる場合があります。特に、市場環境の変化や景気後退などで収益性が悪化した局面では、高いランニングコストが事業の負担として重くのしかかります。
一方で、ランニングコスト管理は環境面・社会面の取り組みとも関連します。たとえば、電力消費の削減やクラウド活用による設備集約は、コスト削減であると同時に環境負荷の低減にもつながります。適切な労働時間管理や過度な属人化の解消も、人的コストと働きやすさのバランスを整える取り組みと言えます。ランニングコストとビジネスの持続可能性は、企業の長期的な成長と信頼性を支える重要なテーマです。
ランニングコストマネジメントは、企業経営において次のようなメリットをもたらします。
これらを実現するためには、経営層がランニングコストの重要性を認識し、現場の担当者と連携しながら継続的に改善を進めていくことが求められます。ランニングコストマネジメントは、一度取り組めば終わりという性質のものではありませんが、仕組みとして定着させることで、企業の競争力や収益性、持続可能性を着実に高めていくことができます。
ランニングコストとは、システムやサービスを導入した後に継続的に発生する運用・保守費用の総称です。保守管理費用、ライセンス料、ハードウェア更新費用、電力料金、人件費など、日々の運用で発生する多くの費用が含まれます。
ランニングコストは、単に削減すべき「経費」として捉えるのではなく、長期的な視点でビジネスの競争力や持続可能性を左右する重要な要素として扱う必要があります。構成要素や計算方法を理解し、自社にとっての主要なコスト要因を洗い出したうえで、クラウド活用や運用自動化、省電力化などの施策を組み合わせながら最適化を進めていくことが重要です。
また、ランニングコストはイニシャルコストと合わせてTCOとして評価することで、より妥当な投資判断につながります。ランニングコストマネジメントを継続的な取り組みとして位置づけることで、企業は収益性と競争力、そしてビジネスの持続可能性を同時に高めていくことができるでしょう。
システムやサービスを導入した後、運用・保守を継続するために発生し続ける費用の総称です。
イニシャルコストは導入時の初期費用で、ランニングコストは導入後に継続的に発生する運用・維持費用です。
保守管理費用、ソフトウェアライセンス料、ハードウェア更新費用、電力料金、人件費などが含まれます。
一般的には3~5年程度のシステムライフサイクルを前提に、トータルでの負担を見積もることが推奨されます。
システム構成と運用体制を具体的に整理し、各項目の年間費用を洗い出して合算することが重要です。
必ずしも下がるとは限らず、利用量や設計次第でオンプレミスより高くなる場合もあります。
コスト削減を優先しすぎると、品質やセキュリティが低下するため、バランスを取ることが重要です。
企業規模に関わらず必要であり、特にリソースに制約のある中小企業ほど重要になります。
TCOはイニシャルコストとランニングコストを合算した総所有コストを示します。
まずは現状の費用構成を可視化し、どの項目にどれだけのコストがかかっているか把握することから始めます。











