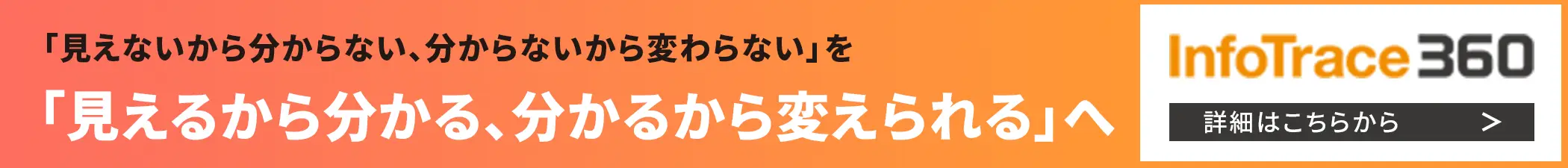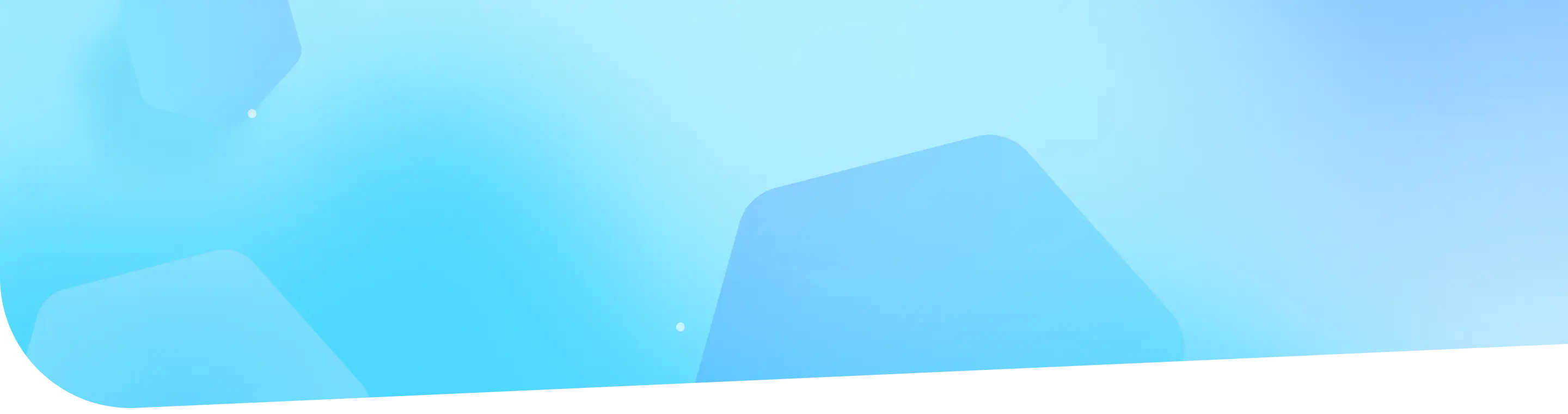
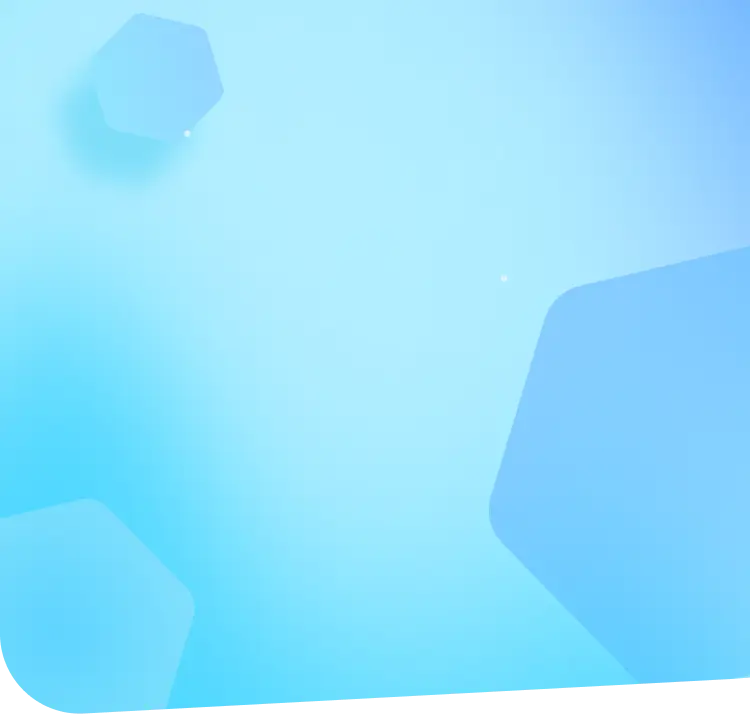
企業のセキュリティ課題として挙げられることの多い「シャドーIT」。用語としては知られていても、「どこからがシャドーITなのか」「何が危ないのか」が曖昧なまま、対策が後回しになっているケースは少なくありません。
シャドーITは「一部の人が勝手にやっている話」ではなく、業務の効率化や現場の工夫をきっかけに発生しやすいものです。だからこそ、実態を把握したうえで、技術対策だけに頼らず、運用と教育まで含めて対策を組み立てることが大切です。
この記事では、シャドーITの概要、セキュリティリスク、発生原因、BYODとの違い、企業が取るべき対策の考え方、進め方の手順までを整理します。読み終えたときに、「まず何から手を付ければよいか」を判断しやすい状態を作ることを狙いとします。
この章では、シャドーITが何を指すのか、どこまでが対象になり得るのかを整理します。
シャドーITとは、企業が許可していない、または従業員が利用していることを企業側が把握・管理できていないITシステム、クラウドサービス、ソフトウェア、デバイスなどを指します。代表例としては、従業員が独自に業務利用している私物スマートフォン、個人アカウントのクラウドストレージ、個人向けチャットツール、無許可の生成AIサービスなどが挙げられます。
スマートフォンやクラウドサービス自体が悪いわけではありません。問題は、情報システム部門やセキュリティ部門が利用実態を把握できないために、事故を防ぐための対策(認証、アクセス制御、ログ取得、設定標準化など)を揃えにくくなる点です。さらに、事故が起きたときの対応(封じ込め、調査、報告、再発防止)も準備しづらくなります。
また、シャドーITは「未承認ツール」だけを指すとは限りません。たとえば、企業が利用を許可しているSaaSであっても、個人アカウントで契約して使う、共有範囲や外部連携、MFAなどの設定が管理されていない、監査ログが取れていないといった状態は、結果として管理できない運用になり、シャドーITと同じ種類のリスクを生みます。
「知らないうちに」リスクを抱え、結果的に大きなセキュリティインシデントに発展しやすくなるため、シャドーITは組織として向き合うべきテーマです。

シャドーITの本質は、「便利な道具を使うこと」ではなく、組織が把握できず、管理できない状態が生まれることです。管理できない状態では、次のような運用上の問題が起こりやすくなります。
この章では、シャドーITが具体的にどのような事故につながり得るのかを、リスクの種類ごとに整理します。
企業の許可なく使用されるサービスやデバイスでは、セキュリティポリシーに沿った対策が前提になりません。その結果、情報漏えい、不正アクセス、アカウント乗っ取り、マルウェア感染などの被害につながりやすくなります。さらに、発見が遅れたり、原因特定が難しくなったりする点も、シャドーITのリスクを大きくします。
業務データが企業の管理外に置かれることで、意図しない公開や第三者への共有が起こりやすくなります。たとえば、業務データを個人のメールアドレスや個人向けクラウドストレージに保存した場合、企業側の監査、アクセス制御、DLP(情報持ち出し対策)が効かず、共有設定の誤りなどで外部に露出する可能性があります。
また、個人アカウントのサービスでは、退職、端末変更、パスワード忘れなどのタイミングで、データを回収できない、誰が持っているか分からないといった状態も起こり得ます。これは漏えいの有無にかかわらず、情報資産管理として大きな問題です。
個人アカウントの認証強度が不十分なまま運用されると、攻撃者にとって侵入口になりやすくなります。シャドーITとして利用しているチャットやクラウドストレージが乗っ取られると、保存されている業務情報が盗まれるだけでなく、なりすまし投稿や不正送金誘導などの二次被害に発展するおそれもあります。
特に、個人利用の延長で「弱いパスワード」「MFA未設定」「使い回し」といった状態が残ると、被害が起きる確率は高まりやすくなります。
安全性が確認できないソフトウェアや拡張機能を経由して、マルウェア感染や認証情報の窃取に発展する可能性があります。不要な拡張機能や不審なアプリ、偽サイトなどをきっかけに感染が起こると、社内ネットワークへの侵入や横展開の起点になることもあります。
加えて、クラウドサービス同士の連携(外部アプリ連携、OAuth連携など)が増えるほど、どのサービスにどの権限を渡しているかが見えにくくなります。侵害が起きた場合に、影響範囲の見積もりや遮断が難しくなる点にも注意が必要です。
状態が分からない端末が社内ネットワークに入ると、感染端末が侵入口になる可能性があります。管理外端末は、パッチ適用状況やEDR導入状況が不明であり、攻撃者にとって狙いやすい経路になり得ます。
また、端末を社外に持ち出す運用では、紛失や盗難も現実的なリスクです。暗号化、画面ロック、リモートワイプなどがない場合、端末内データやセッション情報が悪用されるおそれがあります。
生成AIやクラウドサービスが身近になったことで、シャドーITは「ツールの未承認」だけではなく、入力や連携が見えない状態として発生しやすくなっています。たとえば、生成AIに業務資料を入力した場合、企業側が入力内容や保管状況を追えないまま運用が続くことがあります。
また、外部アプリ連携やOAuth連携が増えるほど、いつ・誰が・どの権限を許可したかが把握しづらくなります。連携先の洗い出しができないと、侵害時の遮断や影響範囲の特定が難しくなるため、連携を増やすほど「見える化」の重要性は上がります。
この章では、シャドーITが「起きてしまう構造」を整理し、対策を考えるための前提をそろえます。
まず押さえたいのは、シャドーITは「誰かがルールを破ったから起きる」だけの話ではない、という点です。正式な選択肢が業務に合っていない、あるいは必要な判断が間に合わないときに、現場は手元の道具で業務を前に進めようとします。その結果として、管理できない利用が生まれやすくなります。
近年、テレワークの普及やクラウドサービスの業務利用が拡大し、時間や場所にとらわれない働き方が浸透してきました。さらにスマートフォンをはじめとするスマートデバイスの普及もあり、多くの従業員が便利なサービスやアプリを日常的に使っています。
一方で、企業側が正式に導入するには、セキュリティ審査、契約、運用設計、社内合意などが必要です。これらは重要な手続きですが、現場が「今すぐ必要」「手元の道具で何とかしたい」と感じる場面では、手続きの待ち時間そのものが業務の障害になり得ます。
また、「許可されていないサービスを業務に使ってはいけない」という理解が十分に浸透していない場合もあります。さらに、ルールがあっても現場の業務要件を満たせず、結果として抜け道のようにシャドーITが発生するケースもあります。
シャドーIT対策は、単に取り締まる話ではありません。クラウドシフトやスマートデバイス活用を進めるほど、利便性と安全性の両立は難しくなります。組織全体で取り組むべきテーマとして捉えることが、シャドーIT対策の出発点になります。
この章では、混同されやすいBYODとシャドーITの違いを整理し、何が境界線になるのかを明確にします。
モバイルデバイスの普及により、BYOD(Bring Your Own Device)という考え方も広がっています。BYODは、従業員の私物パソコンやスマートフォンなどを業務利用する運用形態です。

従業員の私物デバイスがシャドーITとみなされることがありますが、両者の大きな違いは企業側が許可し、管理できる状態にしているかどうかです。
BYODは、適切な管理とルールが伴えばシャドーITの抑止策にもなり得ます。ただし、そのためには「どの端末を許可するか」「どのデータにアクセスさせるか」「紛失時にどうするか」など、運用設計が欠かせません。
シャドーIT対策は、「止める」「許可する」を決める前に、まず実態をつかむことから始まります。ただし、やみくもに探そうとすると範囲が広すぎて手が止まりがちです。ここでは、シャドーITを見つけるための現実的な観点と、社内で確認しやすいチェック項目を整理します。
ポイントは、ツール名を片っ端から列挙することではありません。「業務データが企業の管理外に出る経路」と、「企業が把握できない認証・連携・端末」に絞って見ていくと、優先順位が付けやすくなります。
シャドーITは、実務上の「よくある行動」に紛れています。まずは次のような行動が常態化していないかを確認します。
洗い出しは「完璧」を目指すほど止まるため、最初は“危険が表面化しやすい箇所”から当たるのが現実的です。次の項目は、部署ヒアリングやログ確認の入口として使いやすいチェック例です。
この章で挙げた項目は、すべてを一度に潰すためのものではありません。まずは「どこに起点があるか」を見つけ、次章以降の対策(許可・標準化・抑止)につなげるための入口として使うのが目的です。
この章では、シャドーITを減らし、万一の事故時にも被害を抑えるための対策を、技術・運用・教育の観点で整理します。
企業が実施すべきシャドーIT対策としては、主に次のようなものが考えられます。
社内ネットワークや業務システムへのアクセスを、許可したデバイスのみに限定することは基本対策です。端末管理(MDM/EMM)や、ネットワーク認証(例:802.1X)などを組み合わせ、接続している端末を一元的に把握できる状態を目指します。
また、端末を許可するだけでなく、端末の状態(暗号化、ロック、OS更新、セキュリティソフトの導入状況など)を条件にアクセスを制御できると、管理外端末が侵入口になるリスクを下げられます。ここで重要なのは、許可した時点で終わりにしないことです。許可後も、状態の変化(OS更新の遅れ、設定変更など)を前提に運用を組み立てます。
クラウドサービス利用が前提の時代では、どのクラウドにアクセスしているかを把握できない状態そのものがリスクになります。CASB(Cloud Access Security Broker)などを活用し、クラウドサービスの利用状況を可視化したうえで、利用可否の制御、アップロード制限、共有制御などを検討しましょう。
シャドーITの「発見」だけで終わらせず、業務上必要なものは正式化(審査、契約、設定標準化)し、不要または危険性が高いものは代替手段を用意したうえで抑止する、という流れにすると現実的です。正式化の際は、共有範囲、外部連携、MFA、監査ログなど「最低限そろえる設定」を決め、部門ごとにばらつかないようにします。
まずは実態把握が重要です。PC操作ログ、プロキシログ、DNSログ、SaaSの監査ログなどを用いて、シャドーITが「どこで」「どの程度」起きているかを把握すると、対策の優先順位が明確になります。
さらに、「使われているサービス名」だけでなく、何が行われているか(アップロード、外部共有、生成AIへの入力など)まで追えると、リスク評価と是正がしやすくなります。把握の目的は監視の強化ではなく、優先順位付けと、事故時に迅速に切り分けるための材料をそろえることです。
シャドーITは、利便性を求めて発生することが多い傾向があります。制限を強めるだけでは、現場が別の抜け道を探してしまい、いたちごっこになりがちです。
たとえば「社内で正式に使えるファイル共有」「外出先でも安全に利用できる業務環境」「申請すれば短期間で利用可否が判断できる仕組み」など、現場が安心して使える選択肢を用意することが、結果的にシャドーITを減らします。代替策がないまま禁止すると、業務が止まるか、別のシャドーITに移るだけになりやすい点に注意が必要です。
技術対策だけでなく、人的対策も欠かせません。デバイスやサービスの利用ルール、データ取り扱いルール、例外申請の手順を明確にし、定期的に周知・教育を行いましょう。
とくに「個人アカウントへの転送」「無許可の生成AIへの入力」「私物端末での機密データ取り扱い」など、事故につながりやすい行動パターンは、具体例を交えて伝えることが効果的です。加えて、現場が困ったときに相談できる窓口(情報システム部門、セキュリティ担当、ヘルプデスクなど)を明確にすると、個人判断の暴走を抑えやすくなります。
この章では、現場の反発や形骸化を避けつつ、シャドーIT対策を継続的に運用できる形にするための進め方を整理します。
重要なのは、発見したシャドーITを「違反」として潰すだけで終わらせないことです。現場の困りごと(速度、手間、機能不足)を拾い、正式な選択肢を整備するほど、対策は持続しやすくなります。
シャドーIT対策は、「禁止すれば終わり」になりにくいテーマです。強く止めるほど、別ルートが生まれたり、現場が黙って使い続けたりして、むしろ把握が難しくなることがあります。ここでは、対策を進めるときに起きやすい“つまずき”を整理し、継続的に運用できる形にするための考え方を補足します。
現場がシャドーITを使う背景には、速度、手間、機能不足など、何らかの理由があります。代替策がないまま止めると、業務が回らなくなるか、別のシャドーITに移るだけになりがちです。止める判断と同時に、「公式に使える選択肢」を用意できるかが重要です。
「これはOKで、これはNG」という基準が曖昧だと、現場は相談しにくくなり、個人判断が増えます。判断が担当者の経験や気分に依存すると、部署ごとの抜け道も生まれます。最初から細かい規程を作り込むより、まずは最低限の判断軸をそろえ、例外を運用で吸収できる形にします。
可視化でシャドーITが見つかっても、「それでどうするか」が決まっていないと、発見が成果につながりません。基本は次の三択です。
この三択を決めるためには、「扱うデータの機密性」「外部共有の有無」「監査ログの可否」「認証の強度」「連携権限の大きさ」といった観点で、簡単にでも評価できる状態が必要です。
教育が「使うな」「危ない」で終わると、現場は萎縮するか、表に出さなくなります。効果を出すには、危険な行動例と同時に、困ったときの相談先、例外申請の手順、公式に使える選択肢をセットで示すことが大切です。
シャドーIT対策は、強さよりも継続性が効きます。禁止と現場の両立でつまずきやすい点を先に織り込んでおくと、対策を継続的に運用しやすくなります。
働き方が多様化し、クラウドやスマートデバイスの活用が当たり前になった現在、シャドーITはどの企業でも起こり得ます。問題は「便利なツールを使うこと」ではなく、企業が把握できず、管理できない状態が残ることで、事故の予防も、事故後の対応も難しくなる点にあります。
デバイスとクラウドの可視化・制御、ログによる実態把握、現場が使える選択肢の整備、ルールと教育を組み合わせることで、シャドーITは現実的に減らしていくことができます。まずは「どこで起きているか」を把握するところから始め、自社の状況に合う形で対策を進めていきましょう。
企業が許可していない、または企業側が把握・管理できていないITシステム、クラウドサービス、ソフトウェア、デバイスなどを指します。ポイントは「ツールの名前」よりも、認証・設定・ログ・事故対応が企業の管理下にない状態が残ることです。
企業のルールに沿った認証、権限管理、ログ取得、設定標準化が行われにくく、情報漏えいや不正アクセスの予防が難しくなるためです。加えて、発見や原因特定が遅れやすく、事故対応が後手に回りやすい点もリスクになります。
個人クラウドへの業務ファイル保存、未承認のチャット利用、私物端末での業務アクセス、無許可の生成AIへの入力などが挙げられます。承認済みSaaSでも、個人契約や設定未統制で管理できない運用になっている場合は、同種のリスクが生じます。
個人契約で利用していたり、共有範囲・外部連携・MFA・監査ログが管理されていない場合は、結果として管理できない運用になり、シャドーITと同じタイプのリスクが生まれます。契約形態と設定・ログの統制が境界線になります。
BYODは企業が私物利用を許可し、端末要件・端末管理・アクセス制御・紛失時対応などのルールと運用を整えている状態です。シャドーITは企業が把握できず、管理できない状態で利用される点が異なります。
禁止だけでは、現場が別の手段に置き換えたり、表に出さなくなったりして、むしろ把握しにくくなることがあります。実態把握と制御に加え、業務上必要な用途には「公式に使える選択肢」と申請・判断の仕組みを用意することが重要です。
利用実態の把握です。プロキシログやDNSログ、SaaSの監査ログ、端末管理情報などから、どのサービスがどの程度使われ、どこでデータの持ち出しや外部共有が起きているかを見える形にします。最初から網羅を狙わず、リスクが出やすい経路から確認します。
利用状況の可視化に加えて、利用可否の制御、アップロードや共有の制限、外部連携(OAuth等)の管理、監査ログの取得を組み合わせる方法が代表的です。業務上必要なものは正式化し、設定とログの統一ルールを決めたうえで管理下に置きます。
許可するだけでは安全になりません。端末要件(更新、暗号化、画面ロック等)を定め、端末管理とアクセス制御を組み合わせ、紛失・盗難時の手順や資格情報の無効化まで含めた運用設計が必要です。許可後の状態変化も前提にして管理します。
危険な行動例(個人メール転送、無許可AI入力、外部共有リンク乱用など)と、例外申請の手順、困ったときの相談窓口、公式に使える選択肢をセットで伝えることが効果的です。注意喚起だけにせず、「どうすればよいか」まで示します。
働き方を可視化し、セキュリティ対策・業務改善を支援するレポートサービス IT360