

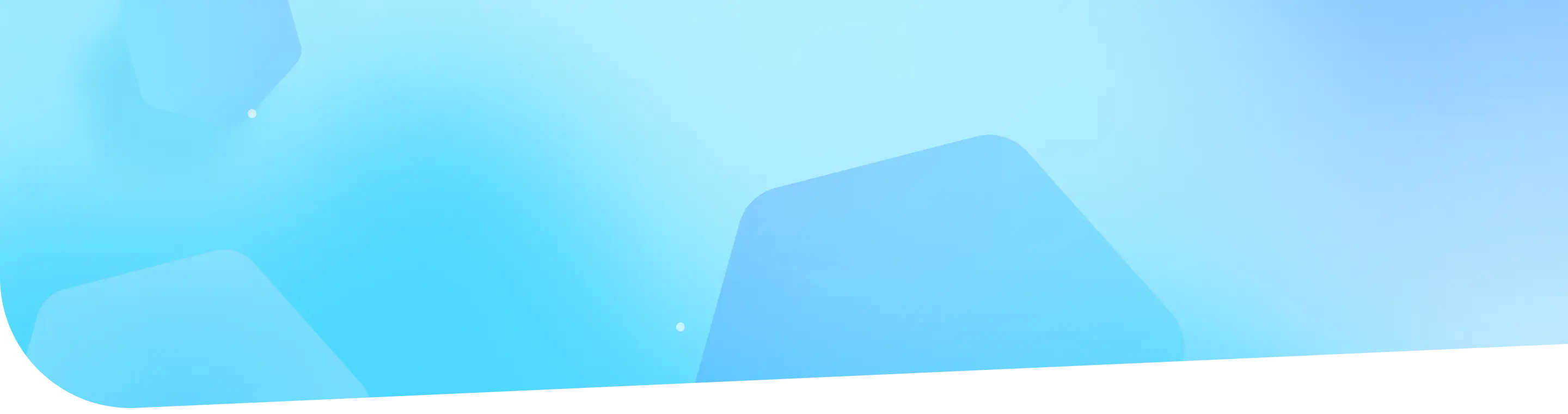
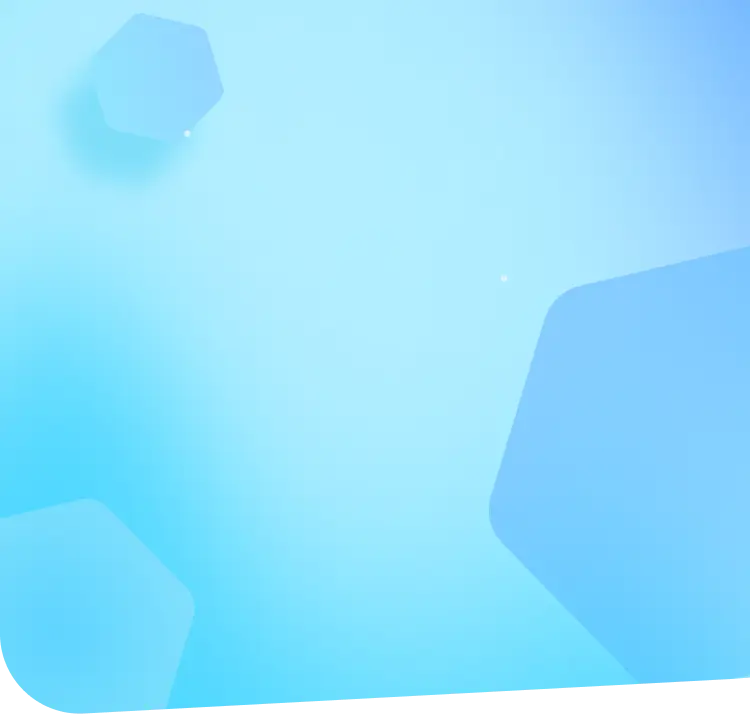
USB Type-Bは、USB(Universal Serial Bus)規格におけるコネクタ形状の一つで、主にプリンターやスキャナーなどの周辺機器側に用いられてきました。本記事では、USB Type-Bの定義や特徴、他のUSB形状との違い、現在の位置づけを整理し、今なお使われ続けている理由と注意点を解説します。USB Type-Cが普及した現在において、USB Type-Bをどのように理解すべきかを確認できます。
USB Type-Bは、USB規格で定義されたコネクタ形状の一つで、主に周辺機器側に搭載されてきた端子です。USB規格は、機器ごとに異なっていた接続方式を統一し、誰でも簡単に機器を接続できるようにする目的で策定されました。USB Type-Bは、その中でも据え置き型の周辺機器での利用を想定した形状として位置づけられています。
USB規格の目的は、機器ごとに異なっていた接続規格を統一し、接続時の手間や混乱を減らすことにありました。USB Type-Bは、周辺機器側の端子として役割を分けることで、誤接続を防ぎ、安定した通信を行うことを意図して設計された規格です。
USB Type-Bの特徴は、上下の角が削られた独特な形状にあります。この形状により、向きを誤って差し込むことを防ぎやすくなっています。また、コネクタ自体が比較的頑丈に作られており、プリンターやスキャナーなど、頻繁に抜き差ししない据え置き型機器での利用に適しています。
USB Type-Bは、USB 1.1やUSB 2.0が普及した1990年代後半から2000年代にかけて、多くの周辺機器で採用されてきました。当時は、機器側とホスト側で役割を明確に分ける設計が重視されており、その考え方を反映した形状がUSB Type-Bです。その後、機器の小型化や多機能化が進み、USB Type-Cなどの新しい形状が主流となりました。
USB Type-Bは、ほぼ正方形に近いサイズで、中央部がわずかに突出した構造を持ちます。この形状は、誤挿入を防ぐだけでなく、接点の安定性を確保する目的もあります。一方で、このサイズと形状は小型・薄型機器には適しておらず、利用範囲が限られる要因にもなっています。
USB Type-Bはコネクタ形状を示す名称であり、転送速度や機能はUSB規格のバージョンに依存します。USB 2.0やUSB 3.0(後にUSB 3.2 Gen1と再定義)など、同じType-Bでも対応する規格によって性能は異なります。
USB規格では、バージョン番号が転送速度や機能の違いを示します。例えば、USB 2.0は最大480Mbps、USB 3.0は最大5Gbpsとされ、世代が新しくなるにつれて高速化が進んできました。ただし、コネクタ形状と規格バージョンは別の概念であり、形状が同じであっても転送速度や機能が同一になるわけではありません。
USB Type-Bは主にUSB 2.0およびUSB 3.0世代で利用されてきました。特にプリンターやスキャナーなどでは、通信速度よりも安定性や互換性が重視されることが多く、その要件に合致していた点が採用理由となっています。
USB Type-Bは、据え置き型の周辺機器との接続を前提に設計されており、用途も比較的明確です。
USB Type-Bは、プリンター、スキャナー、複合機などのオフィス機器で広く使われてきました。また、業務用機器など、物理的な強度や安定した接続が求められる機器でも採用されることがあります。
近年はUSB Type-Cへの移行が進んでいますが、既存設備との互換性や運用上の理由から、USB Type-Bを引き続き採用している機器も存在します。そのため、完全に使われなくなった規格ではなく、用途を限定した形で利用が続いています。
USBには複数のコネクタ形状があり、それぞれ役割や用途が異なります。
USB Type-Aは、主にパソコンなどのホスト側に搭載される端子です。一方、USB Type-Bは周辺機器側に搭載されることを前提としており、接続する側とされる側の役割が分かれていました。
USB Type-Cは、上下の区別がなく、給電や映像出力、高速通信などを1つの端子で扱える汎用性の高い規格です。USB Type-Bはこうした多機能性を持たず、用途が限定される点が大きな違いです。
USB Type-Bは、新しい規格に主流の座を譲りつつありますが、信頼性や既存設備との互換性という点では現在も一定の役割を担っています。今後は、新規採用よりも、既存環境を維持・運用するための接続方式として使われ続けると考えられます。
USB Type-Bは、周辺機器側の接続を前提として設計されたUSBコネクタ形状です。現在ではUSB Type-Cが主流となっていますが、USB Type-Bは堅牢性や互換性の観点から、特定の用途では今も利用されています。特徴と制約を理解したうえで、用途に応じて使い分けることが重要です。
USB Type-Bは、USB規格で定義されたコネクタ形状の一つで、主にプリンターやスキャナーなどの周辺機器側に搭載されてきた端子です。
機器側とホスト側の役割を分け、誤接続を防ぎながら安定した通信を行うために設計された規格だからです。
パソコン側のUSB Type-Aなどとケーブルで接続し、周辺機器とのデータ通信を行う仕組みです。
安定した接続と物理的な耐久性を確保し、業務用や据え置き型機器の運用を支えてきました。
構造が比較的頑丈で、誤挿入しにくく、長期間の利用でも安定しやすい点がメリットです。
形状が大きく、小型・モバイル機器には適していないことや、最新規格と比べて機能が限定される点が挙げられます。
プリンターやスキャナーなど、据え置き型の周辺機器で主に使用されます。
USB Type-Cは多機能で上下の区別がない一方、USB Type-Bは用途を限定した従来型の規格です。
既存機器との互換性や、用途が据え置き型かどうかが判断のポイントになります。
新規採用は減少していますが、既存設備を中心に、当面は使われ続けると考えられます。











