

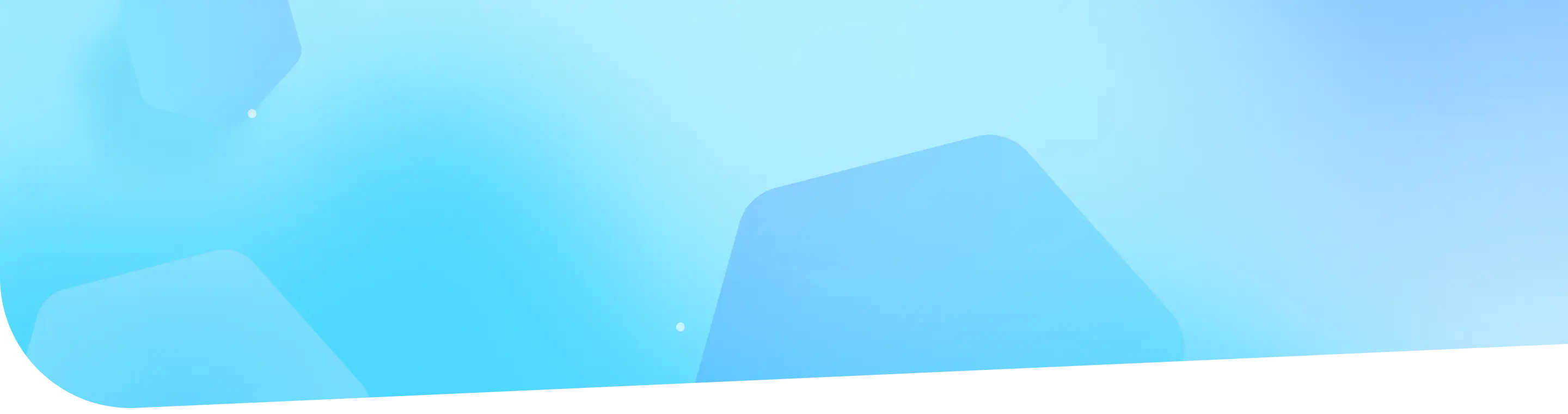
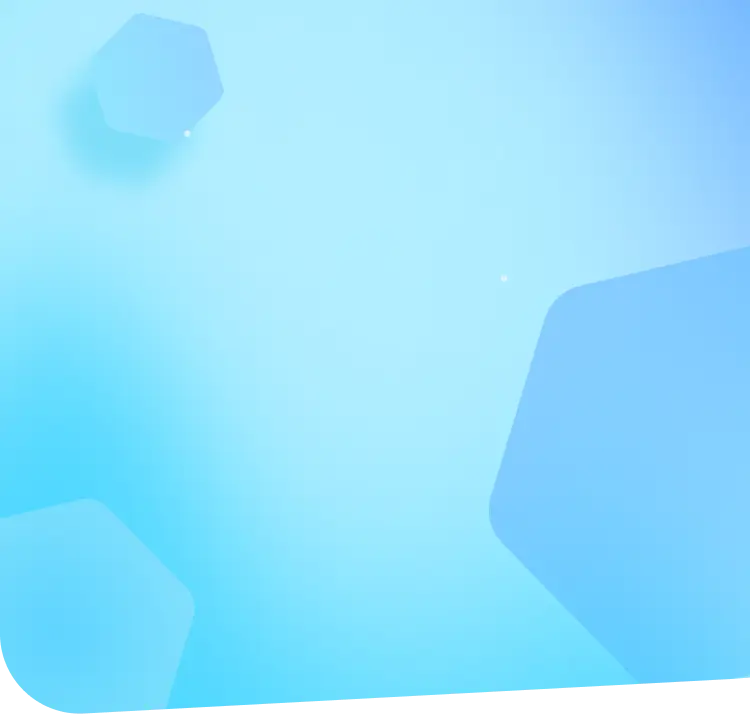
コンピュータウイルスやマルウェアに感染すると、データ破損や情報漏洩だけでなく、業務停止や不正送金など、被害が連鎖するおそれがあります。そうしたリスクを下げる基本が「ウイルススキャン」です。本記事では、ウイルススキャンの仕組み、代表的なスキャン方法、運用時の注意点、そして“スキャンだけに頼らない”補完策までを整理します。読み終えるころには、自分(自社)にとって必要なスキャンの頻度や設定方針を判断できるようになります。
ウイルススキャンは、端末やサーバーに潜むマルウェアを検出し、隔離・駆除するための基盤的な対策です。ただし、万能ではありません。まずは「何を守るために、どこまでをスキャンで担保し、どこからを別の対策に委ねるのか」を理解しておくと、設定や運用がブレにくくなります。
ウイルススキャンの主な目的は、端末やサーバー内に侵入したマルウェアを早期に検出し、被害の拡大を防ぐことです。マルウェアは、従来型の「自己増殖するウイルス」だけでなく、ランサムウェア、スパイウェア、バックドア、キーロガーなど多様化しています。感染後に気づけないと、次のような二次被害につながります。
ウイルススキャンを定期的に実行し、かつ定義ファイル(検出ロジック)を最新化することで、既知の脅威に対する検出率が上がり、初動対応も早くなります。企業の場合は、事故対応だけでなく、監査や社内統制の観点からも「実施していること」を説明できる状態が重要になります。
ウイルススキャンはウイルス対策ソフト(エンドポイント保護)によって実行されます。多くの製品は、次のような複数の検出方式を組み合わせています。
一般的なスキャンの流れは次の通りです。
ここで重要なのは、スキャンは「検出」だけでなく、隔離や修復などの「処置」がセットになって初めて効果を発揮する点です。検出後の動作(隔離にするのか、削除にするのか、管理者承認にするのか)も、運用設計の一部として決めておく必要があります。
ウイルス定義データベース(定義ファイル)は、既知のマルウェアの特徴や検出ルールをまとめた更新情報です。新種のマルウェアは日々増えるため、定義が古いと「スキャンしているのに見つけられない」状態になりかねません。
更新で押さえるべきポイントは次の通りです。
特に企業では「更新されているはず」が事故の原因になります。管理画面で更新状況を可視化し、未更新端末を把握できる運用にしておくと、対策が形骸化しにくくなります。
ウイルススキャンは大きく、オンデマンドスキャン(手動・定期実行)とリアルタイムスキャン(常時監視)に分かれます。
| スキャンの種類 | 説明 |
|---|---|
| オンデマンドスキャン | ユーザーや管理者が手動またはスケジュールで開始するスキャン。端末全体(フルスキャン)や特定のフォルダに対して実行する。 |
| リアルタイムスキャン | ウイルス対策ソフトが常時動作し、ファイルの作成・ダウンロード・実行などのタイミングで自動スキャンを行う。外部デバイス接続時などのイベントにも連動する。 |
基本方針としては、リアルタイムスキャンを常時有効にしつつ、オンデマンドスキャンを「定期検診」として組み合わせるのが実務的です。リアルタイムは入口対策、オンデマンドは“取りこぼしの点検”という位置づけで考えると、使い分けが明確になります。
ウイルス対策は「どれか一つ」で完結するものではありません。端末の利用状況(持ち出し有無、外部ファイルの受け渡し頻度、管理者権限の運用など)を踏まえ、負荷と効果のバランスが取れる組み合わせを選びます。
完全スキャン(フルスキャン)は、端末内の広い範囲を対象に、網羅的にチェックするスキャンです。時間がかかる一方、常時監視では拾いづらい場所(長期保存ファイル、圧縮ファイルの一部など)の点検に向きます。
頻度は一律ではなく、リスクに応じて決めます。目安としては次のように考えると判断しやすくなります。
重要なのは、頻度よりも「確実に回る設計」です。業務時間に重いフルスキャンを走らせると生産性が落ち、結果として無効化されることがあります。夜間や昼休みなど、負荷の影響が少ない時間帯にスケジュールするのが基本です。
クイックスキャンは、感染が起きやすい領域(システム領域、常駐領域、最近使ったファイルなど)に絞って短時間で確認する方法です。日次で回しやすく、端末の状態を“こまめに点検”する用途に向きます。
運用の例としては「毎日クイックスキャン+週1回フルスキャン」が分かりやすい組み合わせです。モバイル端末やノートPCなど、常に業務外に出る端末は、クイックスキャンの頻度を上げる判断も有効です。
個別スキャンは、受領ファイルや怪しいファイルなど、対象を絞って手動でスキャンする方法です。次のような場面で効果的です。
個別スキャンは“事故の入口”を塞ぐ動きになりやすいため、利用者向けに「開く前に右クリックでスキャン」といった手順を周知しておくと実効性が上がります。
USBメモリや外付けストレージなどの外部デバイスは、マルウェアの持ち込み経路になりやすいため注意が必要です。自動スキャンを有効にしておくと、接続直後にチェックでき、持ち込みリスクを下げられます。
あわせて、運用として次の観点も検討しておくと安全側に寄せられます。
外部デバイス経由の感染は、ルールの徹底が難しい領域です。技術設定と運用ルールをセットにすることで、実務として成立しやすくなります。
ウイルススキャンは「入れて終わり」ではありません。設定を誤ると、性能低下や誤検出が増え、現場で無効化されてしまうこともあります。ここでは、運用上の落とし穴になりやすいポイントを整理します。
製品選定では、検出率だけでなく運用性も含めて判断することが重要です。企業利用でよく見られる評価軸は次の通りです。
「評価が高いから」という理由だけで決めると、運用に乗らないケースがあります。自社の端末台数、ネットワーク環境、管理体制(誰が見るか)まで含めて選ぶのが現実的です。
導入後の設定こそが効果を左右します。最低限、次の項目は“有効化されているか”を確認しましょう。
企業では、例外(除外設定)の扱いも重要です。業務アプリや開発ツールが誤検出されることはありますが、例外を増やしすぎると“穴”になります。例外を作る場合は、理由と期限、見直し担当を明確にしておくと安全です。
偽陽性(誤検出)とは、無害なファイルをマルウェアとして判定してしまうことです。誤検出はゼロにできません。重要なのは、事故として扱わず、手順として処理できる状態にすることです。
特に業務停止につながる誤検出が起きると、現場は対策ソフトを“敵”と感じがちです。あらかじめ「誤検出時の連絡先」「隔離解除の判断基準」「復旧手順」を決めておくと、無効化の発生を抑えられます。
フルスキャンはCPUやディスクI/Oを使うため、端末が重くなることがあります。対策としては次のような工夫が有効です。
重要なのは、「負荷が高いから止める」ではなく「負荷が高くならない形で回す」ことです。運用継続ができて初めて、スキャンは防御として機能します。
ウイルススキャンは重要ですが、それだけで全ての攻撃を防げるわけではありません。近年は、正規ツールの悪用、ゼロデイ攻撃、フィッシングによる認証情報窃取など、スキャン単体では止めにくい手口も増えています。ここでは、スキャンと相性のよい補完策を紹介します。
脆弱性を突く攻撃は、マルウェア感染の主要経路の一つです。OSやソフトウェアを最新に保ち、セキュリティパッチを適用することで、攻撃の入口を減らせます。
「スキャンで見つけて対処する」より、「入らないようにする」ほうが復旧コストは小さくなります。
メールは依然として主要な侵入経路です。攻撃者は、添付ファイルやURLを通じてマルウェアを配布したり、フィッシングで認証情報を奪ったりします。基本動作として次を徹底するだけでも、事故は減らせます。
メール対策は“個人の注意力”に依存しがちです。教育だけでなく、迷惑メール対策・添付ファイル無害化など、仕組み側の対策も併用すると現実的です。
悪意あるサイトは、ユーザーを誘導して不正プログラムを実行させたり、脆弱性を突いて感染させたりします。一般的な対策としては次の通りです。
“うっかり”はゼロにできません。ウェブフィルタリングやDNSによるブロックなど、組織で守れる仕組みを入れると、現場の負担を下げつつ安全性を上げられます。
攻撃の多くは、人の判断ミスや手順の抜けを突いてきます。従業員の意識向上と、具体的な行動ルールの定着は、技術対策と同じくらい重要です。
技術対策と人的対策を組み合わせ、多層防御として運用することで、ウイルススキャンの効果も活きてきます。
ウイルススキャンは、端末やサーバーを安全に保つための基本的な対策です。一方で、設定や更新、運用が伴わなければ効果は落ちます。リアルタイムスキャンを有効にし、クイックスキャンとフルスキャンを無理なく回せる形で組み合わせることが、実務での第一歩です。
あわせて、誤検出への対応手順、スキャン負荷への配慮、アップデートやメール対策といった補完策を整えることで、スキャン単体では止めにくい脅威にも備えられます。自社の利用実態とリスクを踏まえ、「回る運用」に落とし込むことを意識しましょう。
端末内のファイルや挙動を確認し、マルウェアを検出して隔離・削除などの処置を行うものです。
感染リスクは下がりますがゼロにはなりません。更新と設定、補完策の併用が必要です。
基本は有効にすべきです。無効化するとダウンロードや実行時の検知が遅れやすくなります。
端末の利用状況によりますが、月1回〜週1回を基準に、外部ファイルが多いほど頻度を上げます。
日常点検はクイックスキャン、網羅的な点検はフルスキャンという役割分担が基本です。
新種の脅威は日々増えるため、定義が古いとスキャンしても検出できない可能性が高まります。
範囲を最小にし、根拠を確認してから行うべきです。恒久除外は穴になり得ます。
業務外時間帯にスケジュールし、優先度調整や対象見直しで負荷を下げるのが有効です。
接続時の自動スキャンを有効にし、許可デバイスの限定や自動実行の無効化も検討します。
OSとソフトの更新、メール対策、危険サイト対策、教育と報告手順の整備が重要です。











