

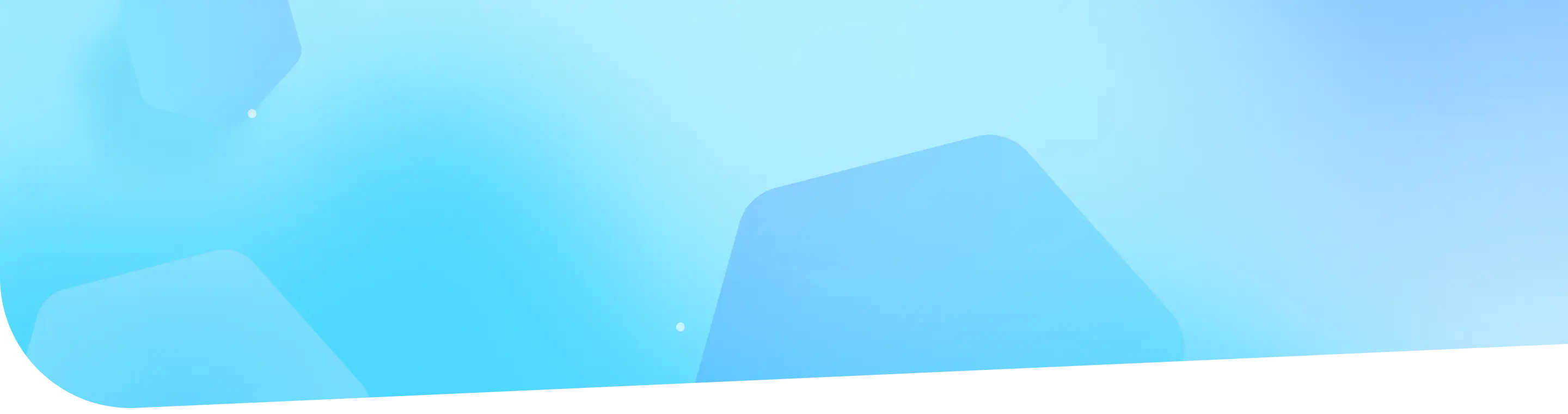
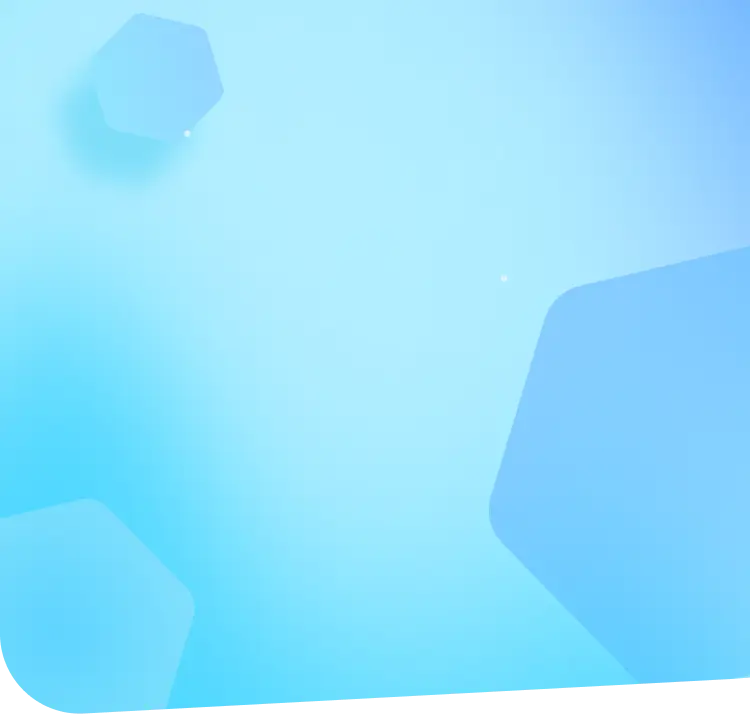
UnsplashのOMAR SABRAが撮影した写真
商品管理に欠かせないJANコードですが、その仕組みや活用方法を社内で正しく説明できる人は、意外と多くありません。この記事では、JANコードの基本から実務での活用方法、導入時のメリット・デメリット、取得手順までを、現場目線で分かりやすく整理して解説します。自社の商品管理や販売管理の見直しを検討している方は、ぜひ参考にしてみてください。
JANコードは、日本で広く使用されているバーコード規格の一つです。商品の識別や在庫管理、POSシステムでの売上管理など、流通や小売業界において重要な役割を果たしています。ここでは、JANコードの意味や基本的な仕組みについて解説します。
JANコードとは、Japanese Article Numberの略称で、日本で使用される商品識別用バーコードを指します。世界的に使用されているGS1(グローバル・スタンダード・ワン)が定めた国際標準(EAN/UPC)に基づいており、日本国内での商品識別に用いられています。
JANコードの主な役割は以下の通りです。
これらの役割により、流通や小売業界における業務の効率化とデータの正確性向上に大きく貢献しています。特に複数店舗展開やECと実店舗をまたぐ販売を行う企業にとっては、共通の「商品ID」として欠かせない存在です。
JANコードは、黒と白の縞模様(バー)で構成されており、その配列によって数字を表現しています。JANコードには、8桁(JAN-8)と13桁(JAN-13)の2種類があります。
| 種類 | 桁数 | 主な用途 |
|---|---|---|
| JAN-8 | 8桁 | 小型商品などスペースが限られたパッケージ向けに用いられてきた短縮コード |
| JAN-13 | 13桁 | 一般的な流通・小売全般で利用される標準的な商品コード |
現在、新たに付番される標準的な商品には、JAN-13が利用されるのが一般的です。JAN-13は、先頭の数字群に国番号とGS1事業者コード(企業を識別する番号)が含まれ、その後に商品アイテムコード、最後にチェックデジット(入力ミスを検出するための検査用数字)が付きます。
JANコードは、専用のバーコードリーダーを使用して読み取ります。バーコードリーダーは、JANコードの白と黒のバーの幅を光学的に読み取り、それを数字に変換します。この数字列が、商品を一意に識別するためのキー情報となります。
バーコードリーダーには、ハンディタイプやレジに固定されたスキャナ、一括読み取りに対応した産業用スキャナなど様々なタイプがあり、用途や現場の作業環境に応じて選択することが可能です。また、近年はスマートフォンのカメラと専用アプリを使ってJANコードを読み取るケースも増えています。小規模店舗やポップアップストアなどでは、このようなスマホアプリ型POSが手軽な選択肢となります。
JANコードを新しい商品に割り当てる際は、GS1 Japanが定める付番ルールに従う必要があります。主なルールは以下の通りです。
これらのルールを遵守することで、JANコードの一意性と整合性が保たれ、サプライチェーン全体で混乱なく商品を管理することが可能になります。特に、取引先やECモールとデータ連携を行う場合は、付番ルールに沿った運用が前提となります。
以上、JANコードの意味と基本的な仕組みについて解説しました。JANコードは、流通や小売業界になくてはならない重要な規格であり、その理解と適切な運用が求められています。
JANコードは、流通や小売業界において商品管理を効率化する上で非常に重要な役割を果たしています。ここでは、JANコードの様々な活用方法について詳しく解説いたします。
JANコードを活用することで、在庫管理の精度と効率を大幅に向上させることができます。各商品にJANコードを割り当て、バーコードリーダーで読み取ることで、入庫・出庫・棚卸しを素早く正確に行えます。これにより、在庫数の把握がほぼリアルタイムで可能となり、適切な在庫量の維持や欠品・過剰在庫の防止につながります。
JANコードを用いた在庫管理システムを導入することで、例えば次のようなメリットが期待できます。
これらのメリットにより、在庫管理にかかるコストを削減しつつ、欠品による販売機会ロスの抑制にもつながります。
JANコードを活用することで、商品情報を一元的に管理することができます。JANコードは、商品マスターデータの「キー」として機能し、名称・規格・価格・カテゴリー・原材料情報などをひも付ける土台になります。
商品情報をJANコード単位で一元化することで、以下のようなメリットが得られます。
これらのメリットにより、業務の効率化だけでなく、顧客満足度の向上や経営判断の質を高めることが期待できます。
JANコードは、販売管理においても重要な役割を果たします。POSシステムと連携することで、JANコードを用いて商品の販売データを正確に記録・管理することができます。
JANコードを活用した販売管理により、次のような業務が効率化されます。
販売データをJANコード単位で蓄積することで、「この商品がどの地域・どの曜日・どの時間帯によく売れているか」といった分析が容易になり、きめ細かな販売戦略の立案に役立ちます。
JANコードとPOSシステムを連携させることで、販売管理や在庫管理の効率化を一段と進めることができます。POSシステムは、レジでJANコードを読み取ることで商品を特定し、その販売データを自動的に記録します。この販売データは、在庫管理システムと連携させることで、在庫数の自動更新にも活用できます。
JANコードとPOSシステムの連携により、以下のようなメリットが得られます。
これらのメリットにより、業務の効率化だけでなく、顧客の待ち時間短縮やサービス品質の向上にもつながります。
以上、JANコードの様々な活用方法について解説いたしました。JANコードを効果的に活用することで、在庫管理、商品情報管理、販売管理など、様々な業務の効率化と最適化を図ることができます。流通や小売業界において、JANコードは欠かせない存在であり、その活用方法を理解することが重要です。
JANコードを導入することで、以下のようなメリットが期待できます。
これらのメリットにより、流通や小売業界における業務の効率化と最適化を図ることが可能になります。単に「バーコードを貼る」だけでなく、バックオフィス業務全体の見直しとセットで導入を検討すると効果が出やすくなります。
一方で、JANコードの運用には以下のようなデメリットや注意点も存在します。
これらのデメリットを踏まえ、自社の業務特性や規模に合わせてJANコード導入の是非や、導入範囲(自社内のみ/取引先との連携まで含めるか)を検討する必要があります。
JANコードの運用においては、以下のような課題がよく見られます。
これらの課題に対しては、以下のような対策が考えられます。
これらの対策を通じて、JANコード運用における課題を克服し、より効果的な活用を推進していくことが重要です。
JANコードの代替手段として、以下のようなものが存在します。
これらの代替手段は、JANコードとは異なる特徴や利点を持っています。業務特性やニーズに合わせて、最適な商品識別方法を選択することが重要です。ただし、標準化された規格であるJANコードの利点(取引先やシステムとの高い互換性)も大きいため、代替手段との使い分けや併用も含めて慎重に判断する必要があります。
JANコードを取得するには、以下の手順を踏む必要があります。
JANコードの取得には、一定の費用が発生します。GS1 Japanへの加入金や年会費、GS1事業者コード・JANコードの登録料などが必要となります。これらの費用は、企業規模や取得するコードの種類・桁数によって異なります。
また、JANコードの印刷には、一定の品質基準を満たす必要があります。バーコードの印刷品質が悪いと読み取りエラーが発生しやすくなるため、用紙やインク、印刷解像度などにも注意が必要です。
一度割り当てられたJANコードは、原則として変更や再利用ができません。これは、JANコードの一意性を維持し、流通現場での混乱を避けるために必要な措置です。
ただし、以下のような例外的なケースでは、JANコードの変更や再利用が検討されることがあります。
これらのケースにおいても、GS1 Japanへの相談・確認が前提となります。JANコードの変更や再利用を検討する際は、自己判断せずにGS1 Japanに問い合わせることが重要です。
JANコードを取得するには、まずGS1事業者コードを取得する必要があります。GS1事業者コードは、国際的な企業識別コードであり、JANコードの一部として使用されます。
GS1事業者コードは企業単位で付与され、同一企業であれば、複数の商品に同じGS1事業者コードを利用できます。そのうえで、残りの桁を使って商品アイテムコードを設計することで、自社商品を体系的に管理できるようになります。
GS1事業者コードの桁数や付与パターンは、事業規模や想定する商品点数などによって異なります。いずれの場合も、コード体系の設計段階で「今後何点ぐらいの商品を管理するのか」を見据えておくことが重要です。
JANコードに関する問い合わせや相談は、GS1 Japanが窓口となっています。GS1 Japanでは、以下のようなサポートを提供しています。
また、GS1 Japanのウェブサイトでは、JANコードに関する各種情報が公開されています。FAQや申請書類のダウンロード、関連リンク集などが掲載されており、JANコードに関する理解を深めることができます。
JANコードの運用において不明な点や問題が生じた場合は、GS1 Japanに相談することをおすすめします。専門スタッフが制度や実務に基づいて、適切なアドバイスを提供してくれます。
以上、JANコードの基本から活用方法、メリット・デメリット、よくある質問までを網羅的に解説しました。JANコードは流通や小売業界において、商品管理の効率化と最適化に欠かせない存在です。
JANコードの仕組みを正しく理解し、業務特性に合わせて効果的に活用することで、在庫管理・販売管理・商品情報管理の精度と効率を高めることができます。導入時には、GS1 Japanのルールやサポート情報も参照しながら、自社にとって無理のない運用体制を構築することが大切です。
JANコードに関する疑問や課題があれば、社内だけで抱え込まず、GS1 Japanやシステムベンダーに相談しながら進めることで、トラブルを防ぎつつ、より大きな効果を引き出せるでしょう。
JANコードは、商品を一意に識別し、在庫管理や販売管理、POS処理などを効率化するためのバーコードです。
バーコードは情報を線のパターンで表現する技術の総称で、その中でも商品識別に使われる規格の一つがJANコードです。
一般的な商品にはJAN-13が使われ、小さなパッケージなどスペースが限られる場合にJAN-8が利用されます。
GS1 Japanに申請してGS1事業者コードを取得し、そのコードに基づいてJANコードを自社で割り当てます。
GS1 Japanへの加入金や年会費、コード登録料などが必要で、企業規模や取得するコードの種類によって金額が変わります。
JANコードは原則再利用不可であり、異なる商品には別のJANコードを付番する必要があります。
はい、売上集計・在庫管理・棚卸しの効率化など、小規模店舗でも業務負荷軽減やミス削減の効果が期待できます。
必須ではありませんが、モール出店や他チャネルとの連携を考える場合、JANコードを付けておくと管理が容易になります。
社内だけで完結する運用なら可能ですが、取引先やECモールとの連携を考える場合は標準のJANコードが推奨されます。
JANコードの取得方法や運用ルールについては、GS1 Japanに問い合わせることでサポートや最新情報を得られます。











